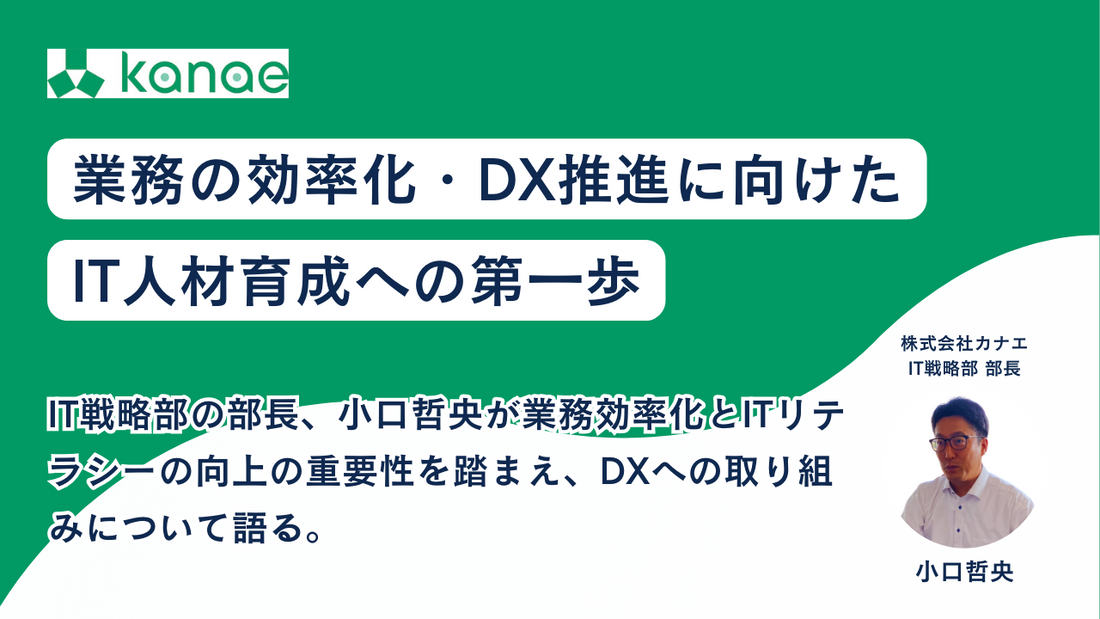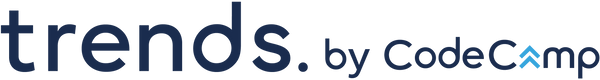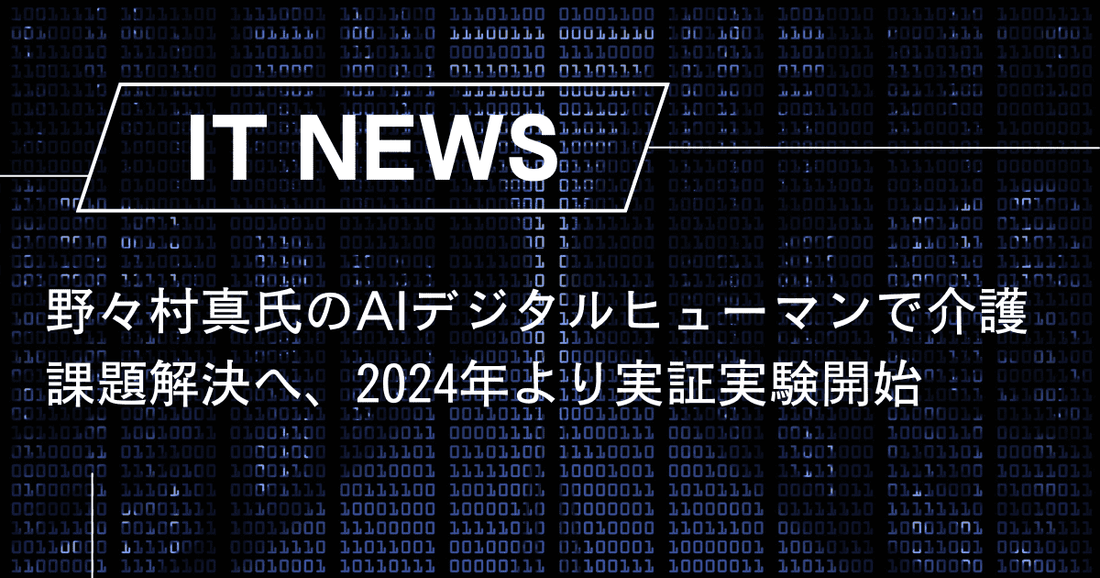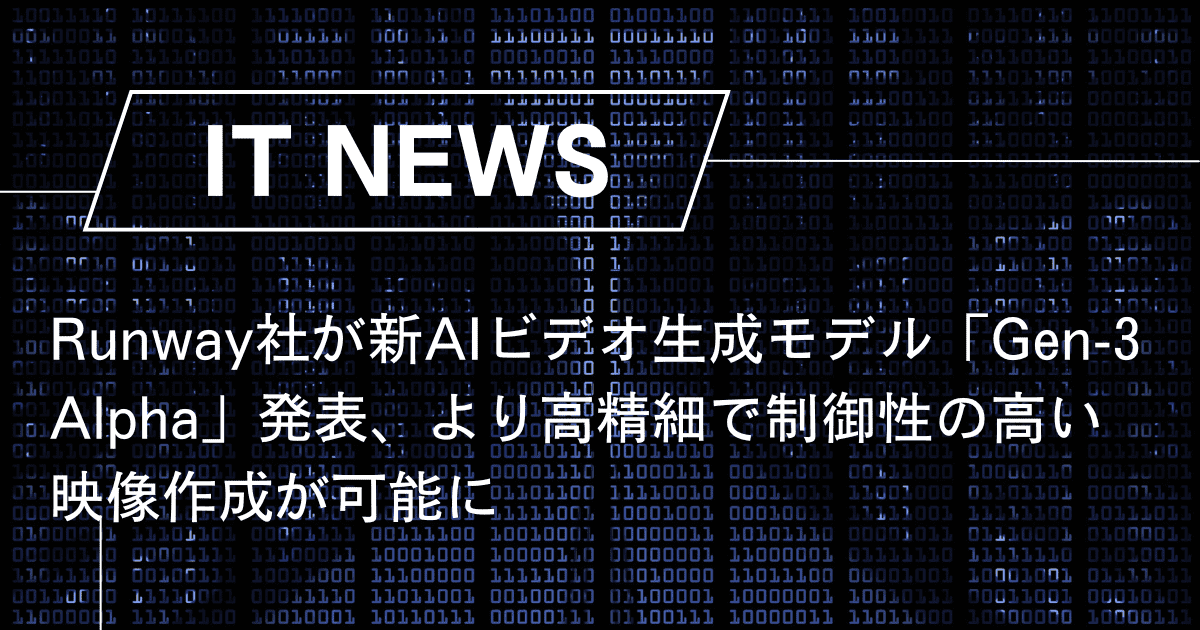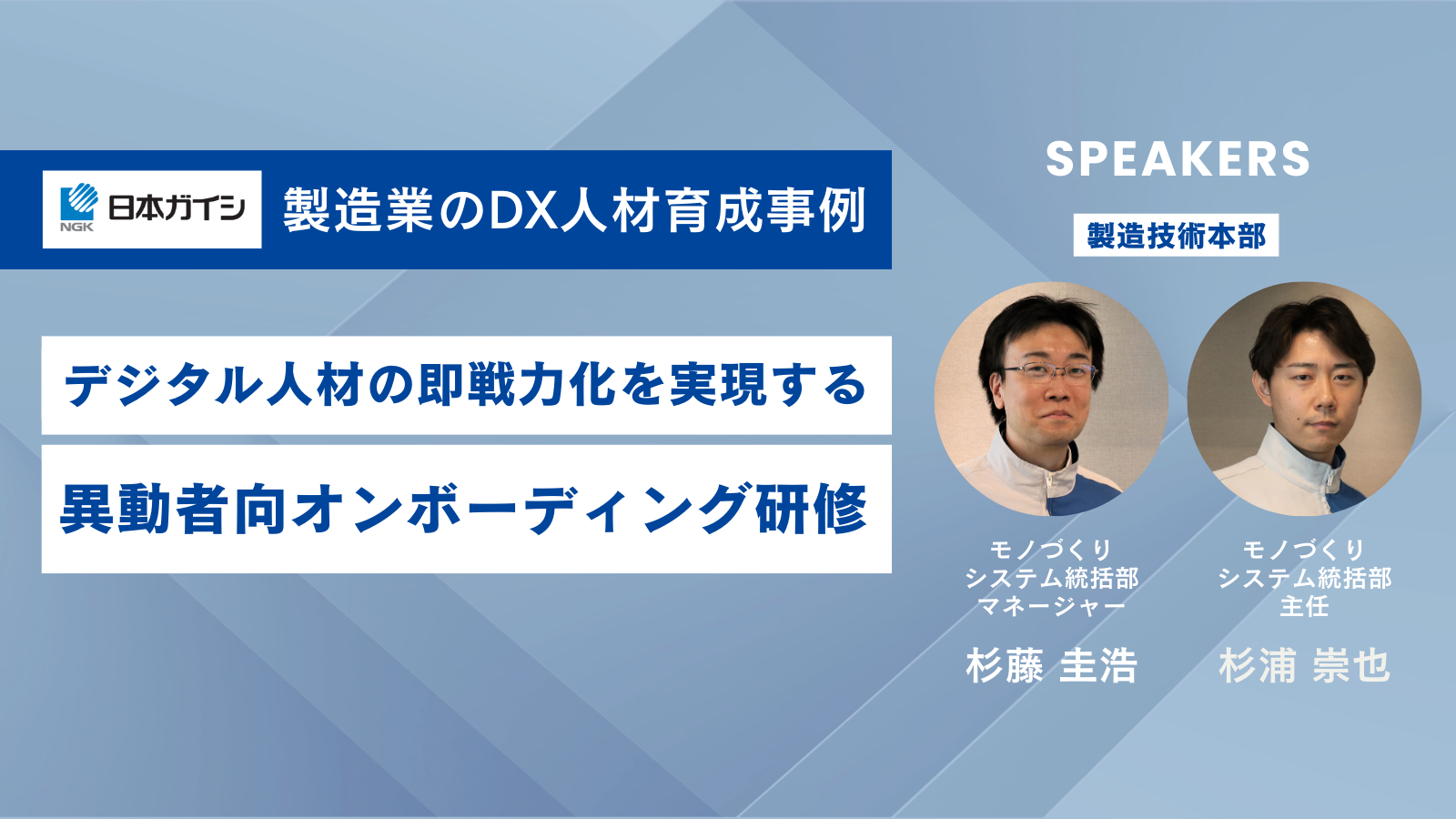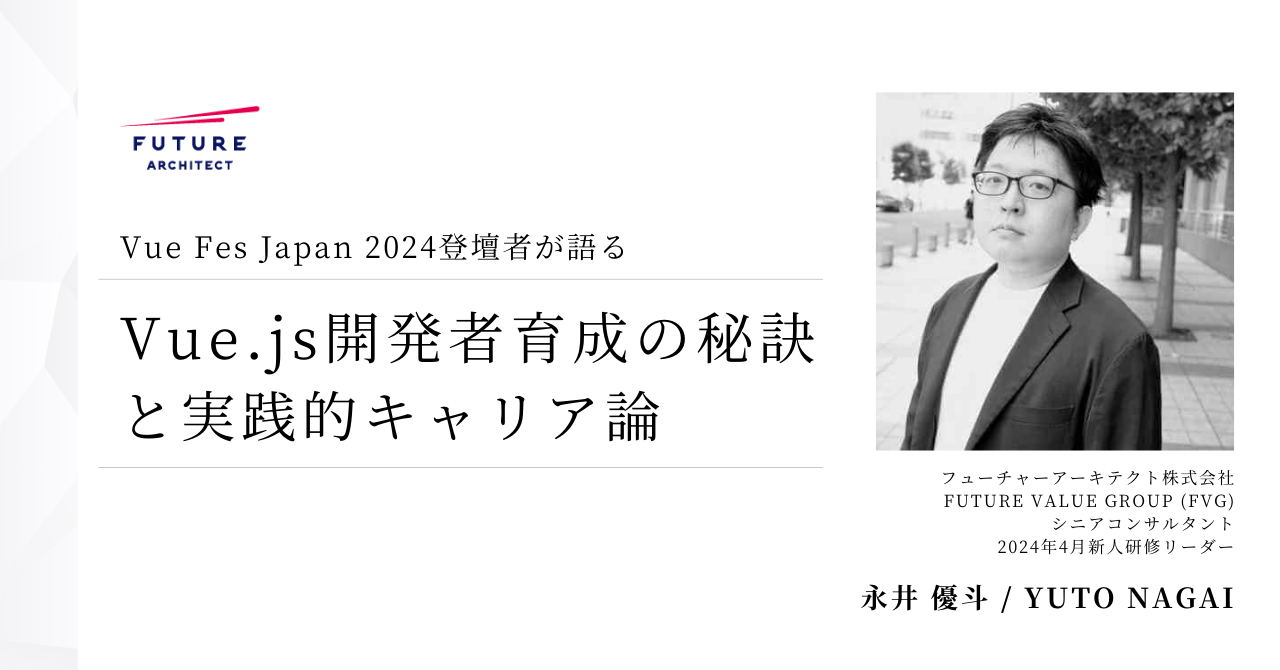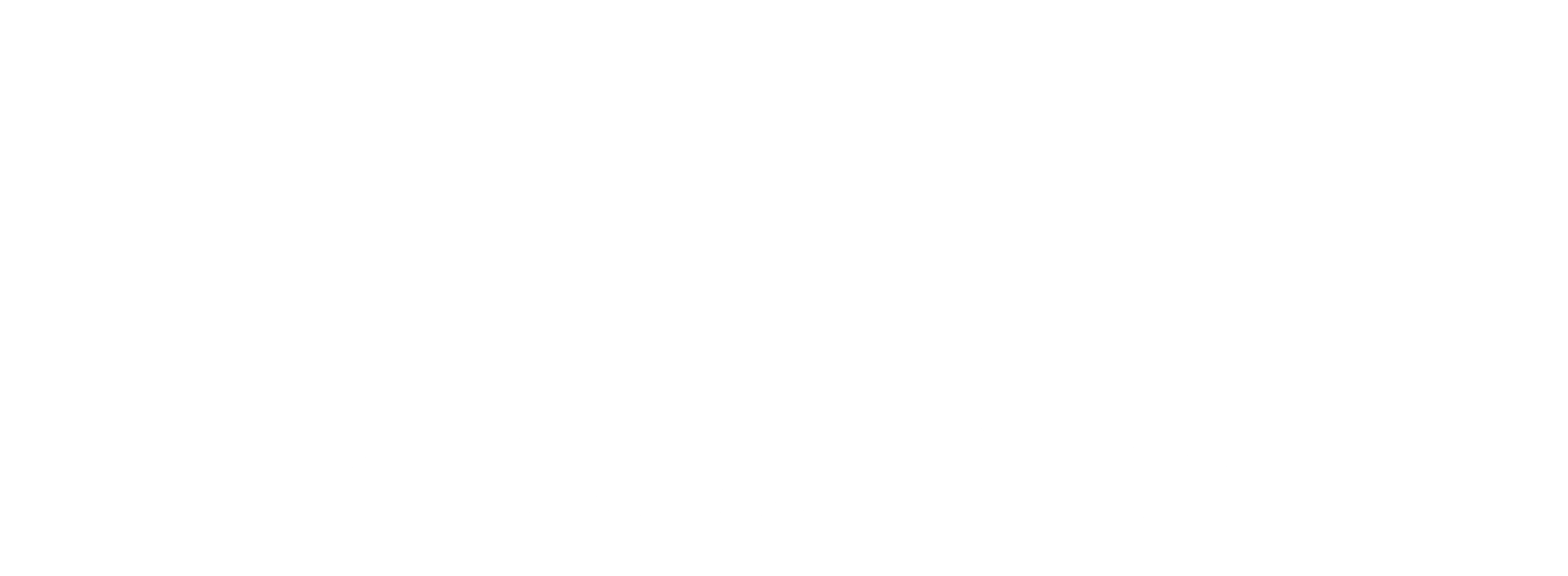【時間がない人向け】記事の3行要約
- AI音声対話型デジタルヒューマンの実証実験を2024年6月13日より開始
- 野々村真氏をモデルとしたAIキャラクターを介護施設で活用し認知機能改善等を目指す
- 9社が参画し2025年の商用導入・販売を目指す
AIデジタルヒューマンを活用した介護課題解決プロジェクト始動
AI活用による高齢社会の介護課題解決に向けて、AIデジタルヒューマンプロジェクト運営事務局は2024年6月13日より実証実験を開始した。このプロジェクトではタレントの野々村真氏をモデルとしたAI音声対話型デジタルヒューマンをシニア向け介護施設で活用し、施設利用者の認知機能の改善やサービス満足度向上を目指すようだ。[1]
プロジェクトにはスターダストプロモーションやSpiral.AI、エスユーエス、学研ココファン、全研ケア、日本ロングライフ、FM、AOI Pro.、TREE Digital Studioの9社が参画。加えて、韓国の大手IT企業ESTsoftも参加している。
実証実験では、AI音声対話型デジタルヒューマンによる1対1の対話提供、集団でのレクリエーション活動での活用などを行う。学研ココファンのココファン池上通り、全研リビングの久喜壱番館・弐番館・参番館、日本ロングライフのロングライフ阿倍野などの施設で実施されるとのこと。
野々村真氏をモデルに選任、AI音声対話で介護現場の負担軽減へ
今回、AI音声対話型デジタルヒューマンのモデルには、数々の情報番組に出演し高齢者にも親しみやすい存在である野々村真氏を選任した。AI技術を活用することで個々の高齢者の会話のテンポに合わせた対話を提供できるほか、音声だけでなく字幕表示によってスムーズなコミュニケーションを実現できる。
野々村氏はAIとなって介護施設のおじいちゃんおばあちゃんと会話できることを楽しみにしていると語る。自身のAIキャラクターがどのようになるのか未知数ながら、新しい挑戦にワクワクしているようだ。
AIによる高齢者とのコミュニケーションが、介護施設利用者の認知機能改善やサービス満足度向上に繋がることが期待されていると同時に、介護現場の人材不足解消にも貢献できる可能性を秘めた取り組みだ。参画各社の協力のもと、2025年の商用導入と販売の実現を目指す。
trends編集部「K」の一言
AI音声対話型デジタルヒューマンを介護現場に導入するこのプロジェクトは、テクノロジーの力で高齢社会の課題解決を図る画期的な取り組みだと言えるだろう。特に個人に合わせた対話や字幕表示など、AIならではのきめ細やかな対応力に大きな可能性を感じる。介護施設利用者の認知機能やQOLの向上に直結するサービスになり得るはずだ。
一方、AIと人間のコミュニケーションにおいては倫理的な課題もつきまとう。プライバシーへの配慮はもちろん、AIに過度に依存することのリスクや人間味あふれる対話を提供し続けることの難しさなど、クリアすべきハードルは少なくない。利用者の尊厳を何より大切にしながら、テクノロジーの恩恵を活かしていくバランス感覚が問われることになるだろう。
とはいえ、高齢化が加速する日本において、介護現場の負担軽減と質の向上は喫緊の課題だ。AIやデジタル技術を上手に活用することで、持続可能でより人間的な介護の実現に近づけるはずである。野々村真氏のような国民的タレントを起用することで、利用者に親しみを持ってもらいつつ、社会全体のAIリテラシー向上にも貢献できるかもしれない。
2025年の商用化に向けて、このプロジェクトから生まれるユーザー体験やノウハウは、他の介護施設や関連事業者にも大いに参考になるだろう。シニアの心に寄り添い、介護をアップデートする新たなソリューションの登場を心から期待したい。
References
- ^ 株式会社FM. 「AI Digital Human Project」. https://fmai.jp/news01.html, (参照 24-06-20).
※上記コンテンツの内容やソースコードはAIで確認・デバッグしておりますが、間違いやエラー、脆弱性などがある場合は、コメントよりご報告いただけますと幸いです。
ITやプログラミングに関するコラム
 3分でWEBサイトを作れる「Wegic」を使ってみた。料金プランや具体的な使い方を詳しく解説
3分でWEBサイトを作れる「Wegic」を使ってみた。料金プランや具体的な使い方を詳しく解説 技術伝承の現実的な課題とは?DXを活用した効果的な解決方法を紹介
技術伝承の現実的な課題とは?DXを活用した効果的な解決方法を紹介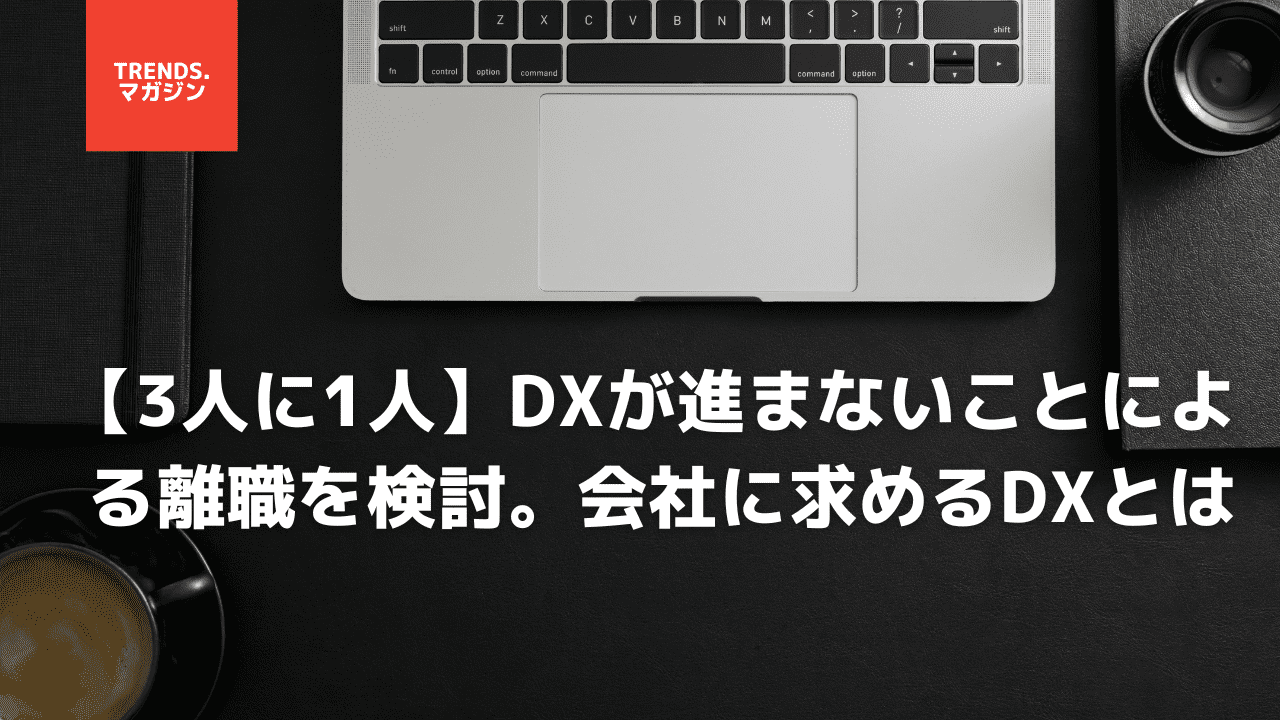 DXのアイデア出しには何が必要?役立つフレームワークも併せて紹介
DXのアイデア出しには何が必要?役立つフレームワークも併せて紹介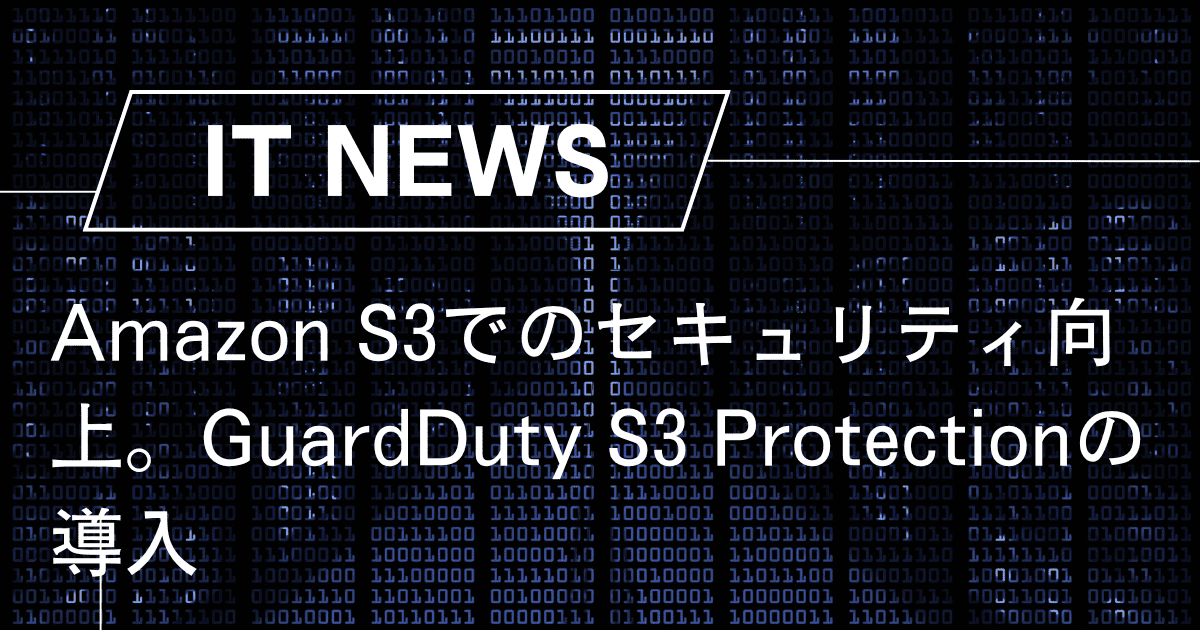 【3人に1人】DXが進まないことによる離職を検討。会社に求めるDXとは
【3人に1人】DXが進まないことによる離職を検討。会社に求めるDXとは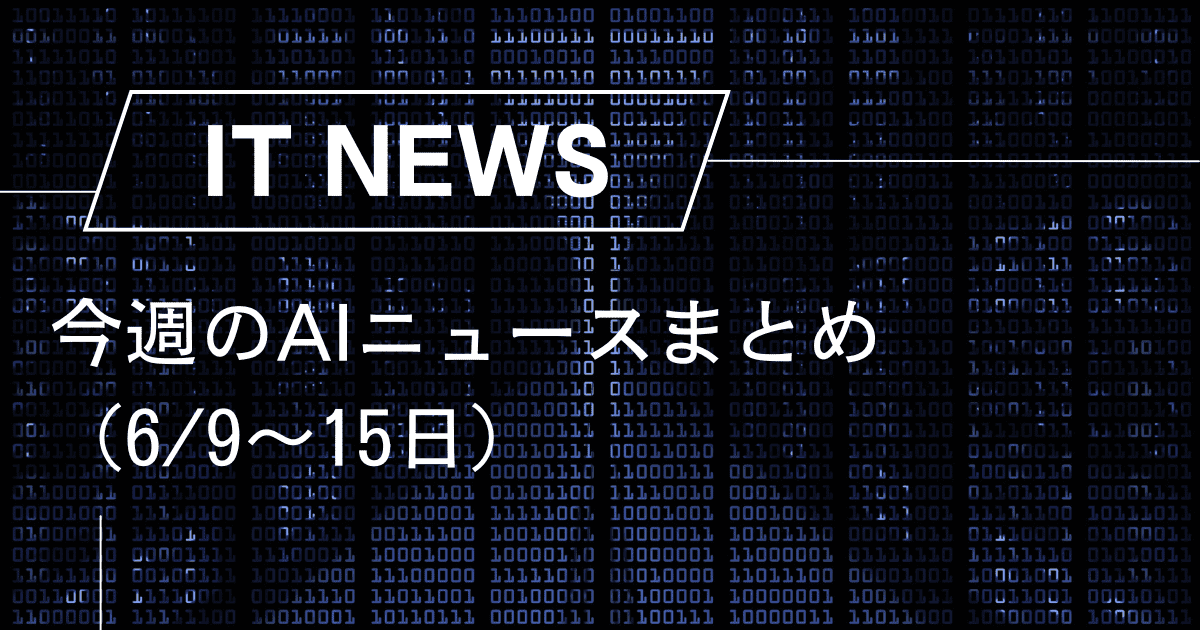 【趣味回】国内No.1のWeb3.0メタバース「XANA」を使ってみた。世界規模のフェス「XANA SUMMIT」の詳細も併せて紹介
【趣味回】国内No.1のWeb3.0メタバース「XANA」を使ってみた。世界規模のフェス「XANA SUMMIT」の詳細も併せて紹介