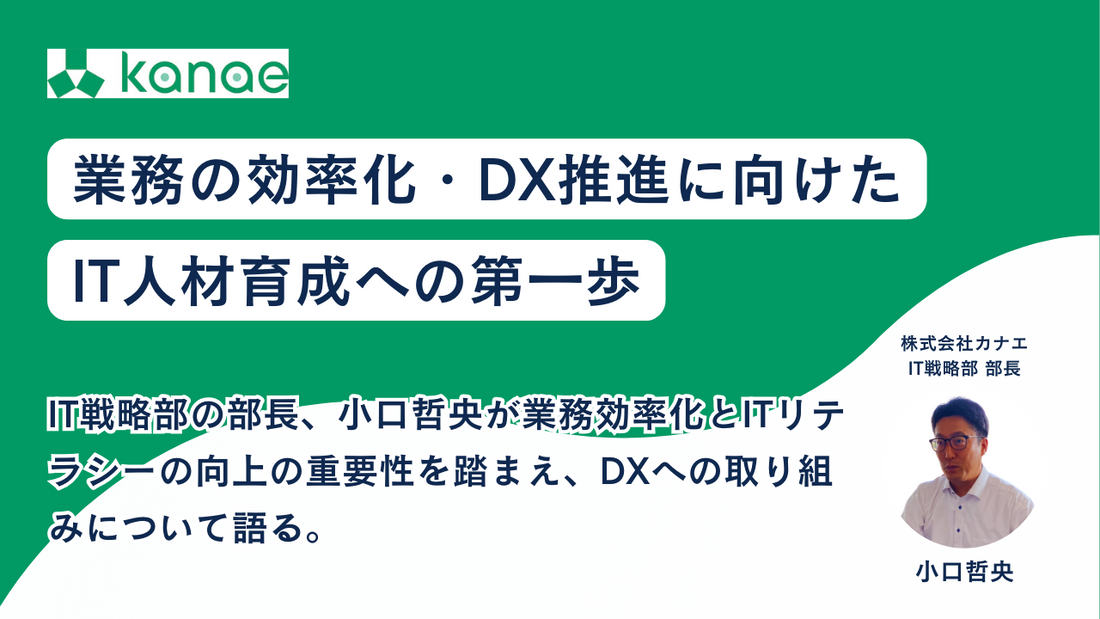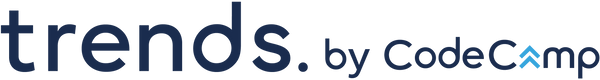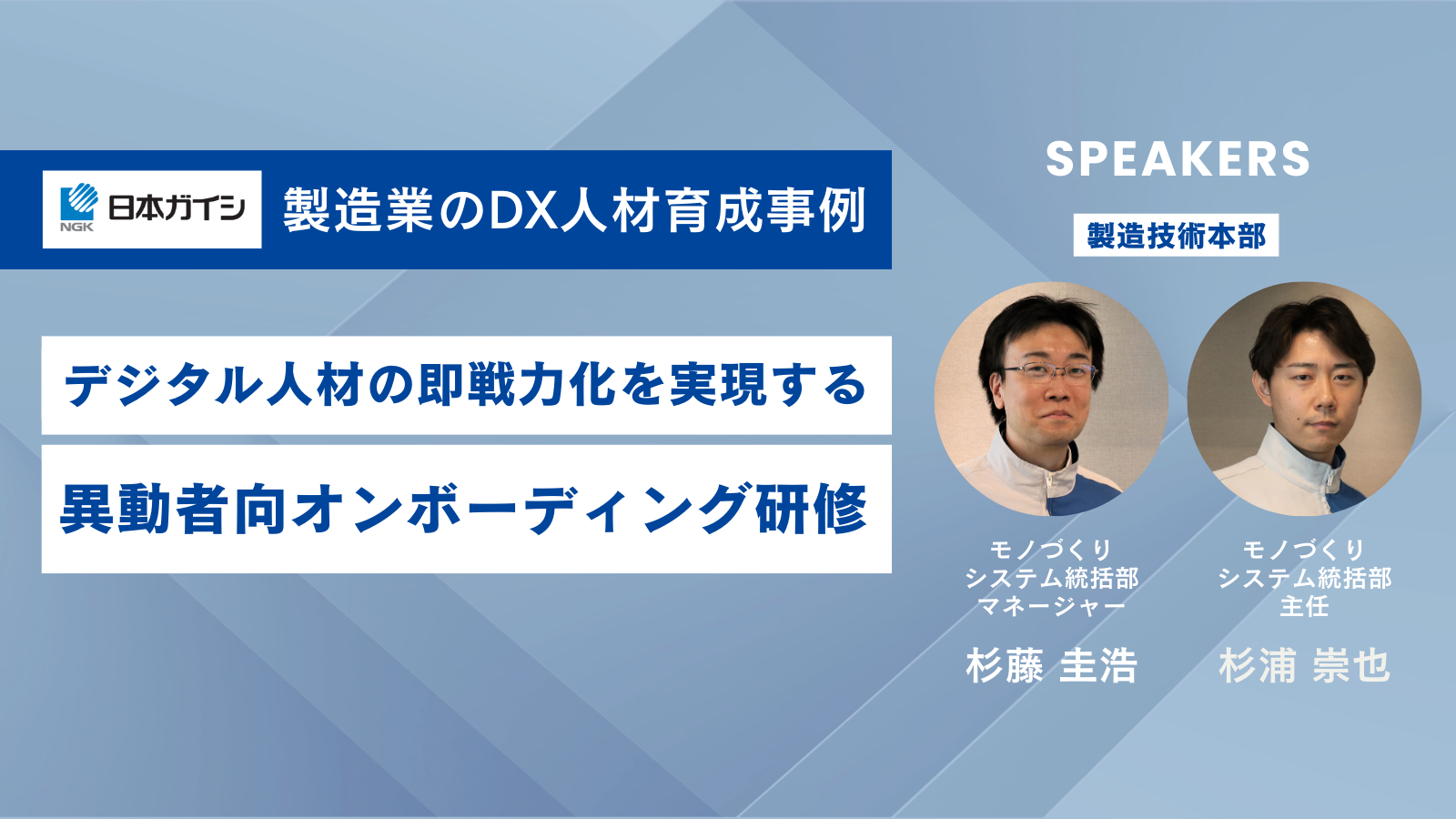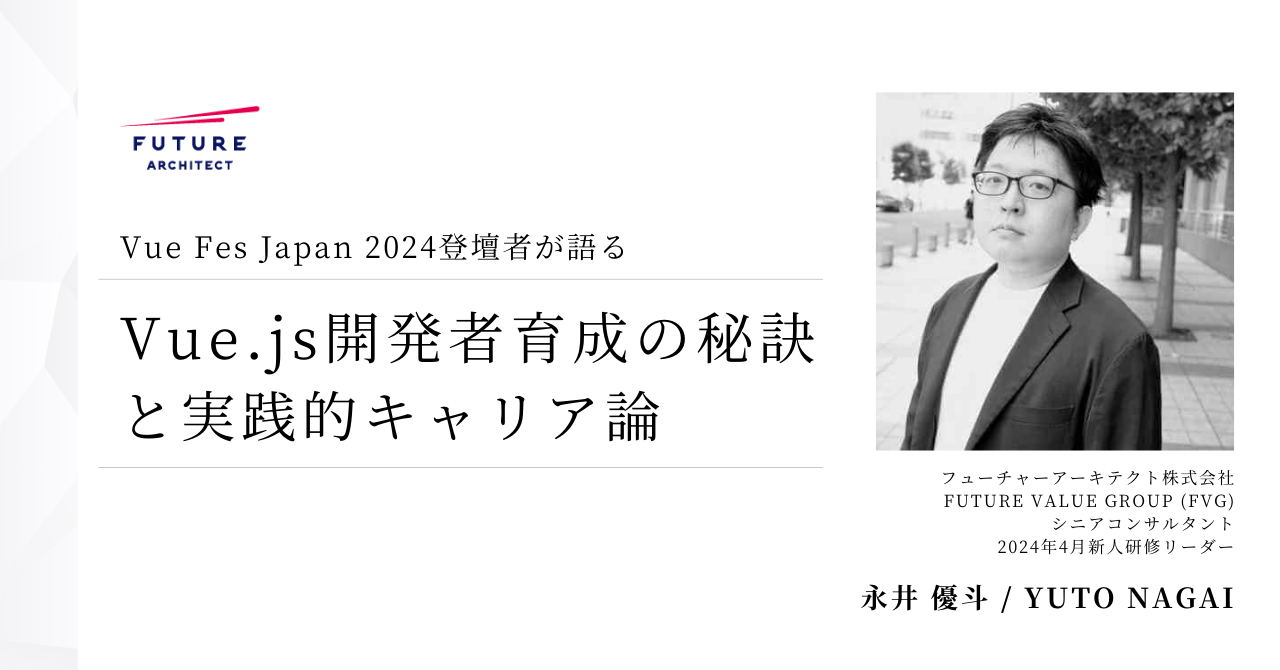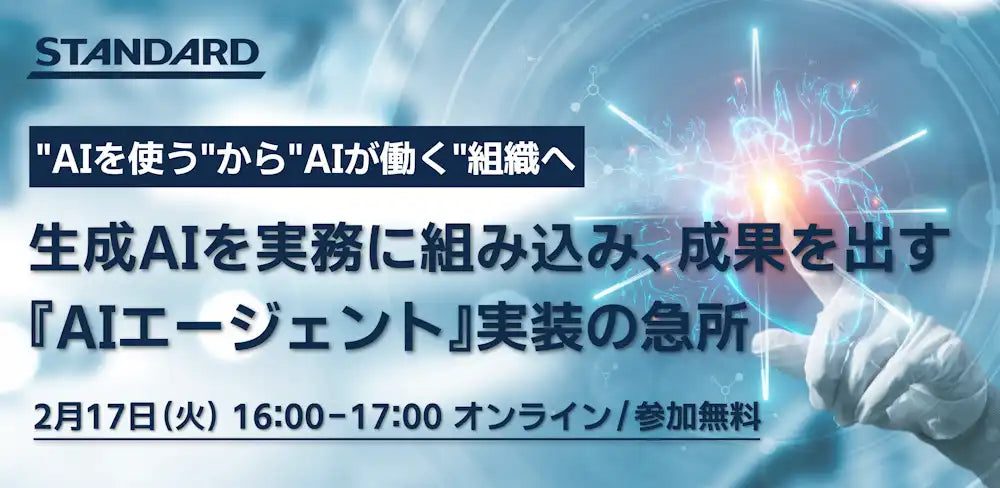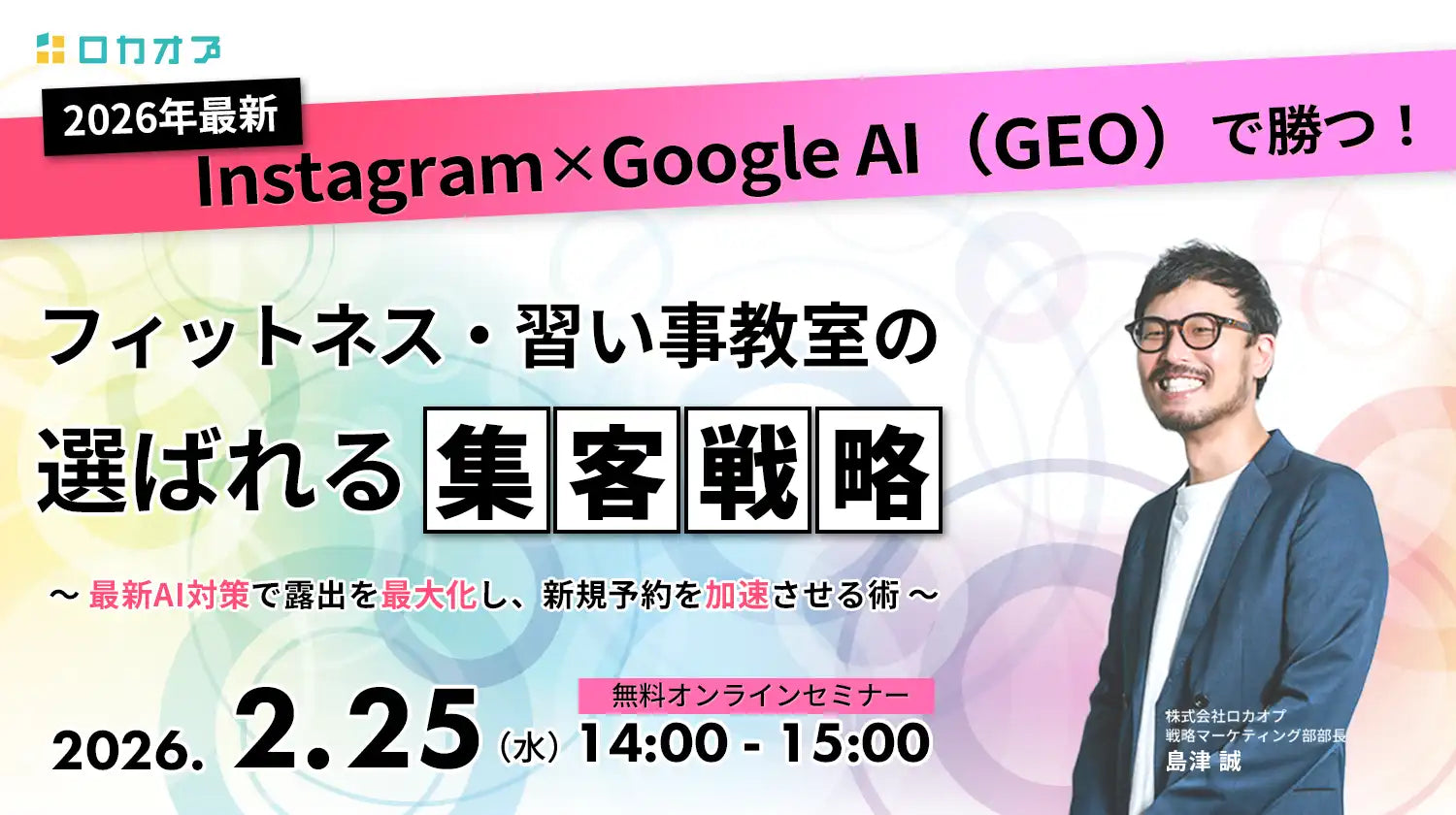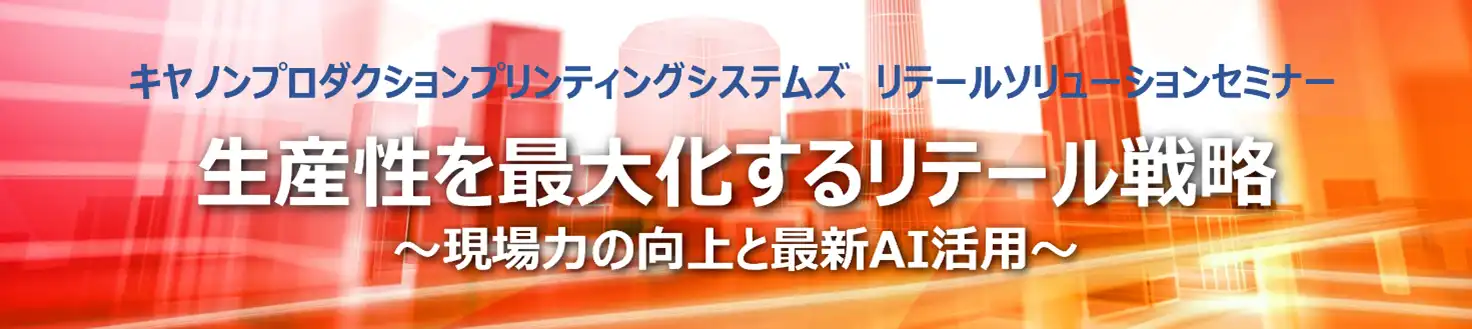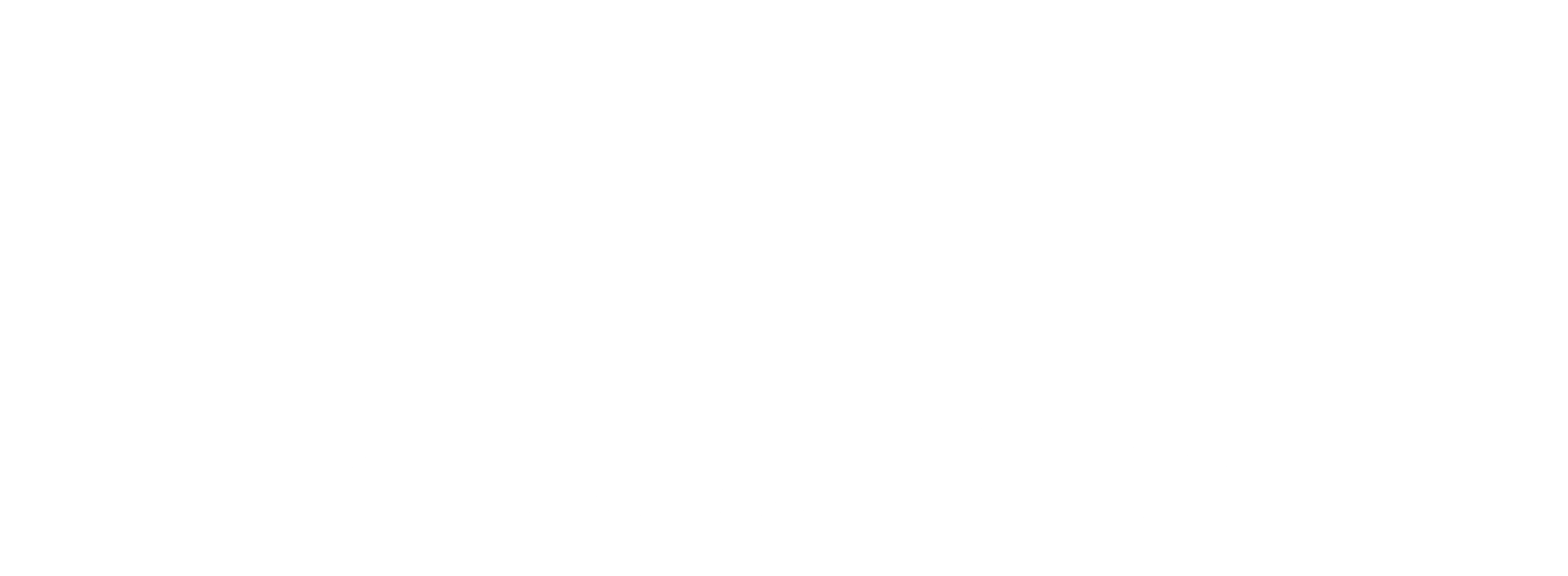スプレッドシートのVARPA関数とは
VARPA関数は、母集団全体に基づいて分散を計算するグーグルスプレッドシートの統計関数です。この関数は、データセット内のテキスト値を0として扱い、数値と混在したデータでも正確に分散を求められます。
VARPAの基本構文はVARPA(値1, [値2, ...])の形式で記述し、最低2つ以上のデータが必要です。この関数は各値の平均からの偏差の二乗の合計を、データの総数で割って分散を計算する仕組みです。
【PR】プログラミングや生成AIを無料で学べる「コードキャンプフリー」
VARPA関数の引数指定方法
VARPA関数における引数の指定では、単一の値や範囲指定の両方で母集団データを入力できます。第一引数のvalue1は必須項目として設定し、第二引数以降のvalue2は任意項目として追加データを指定します。
=VARPA(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
=VARPA(A2:A100)
=VARPA(B1:B50, D1:D20)グーグルスプレッドシートでは30個の引数制限を超えた任意の数の引数に対応しているため、大量データの分析も可能です。複数の範囲や個別の値を組み合わせて指定することで、柔軟なデータ分析が実行できます。
引数として指定するデータが2つ未満の場合には#NUM!エラーが返されるため、最低限のデータ要件を満たす必要があります。データ範囲の指定時には、空白セルや文字列が含まれていても自動的に0として処理されるので事前の前処理は不要です。
VARPA関数とVARP関数の違い
VARPA関数は計算時にテキスト値を0として扱うのに対し、VARP関数はテキスト値に遭遇するとエラーを返します。この仕様により、VARPAは文字列が混在する実際のビジネスデータの分析により適した関数と言えます。
=VARPA("テキスト", 10, 20, 30) // テキストを0として計算
=VARP("テキスト", 10, 20, 30) // エラーが発生VARPA関数は母集団全体の分散を計算するため、標本分散を計算するVARA関数とは分母が異なります。母集団分散ではデータ総数で割る一方、標本分散では自由度を考慮してデータ総数から1を引いた値で割るという数学的違いが存在します。
実際のデータ分析において、調査対象が全体である場合にはVARPAを選択し、一部の標本データから推測する場合にはVARAを使用します。統計分析の目的と対象範囲を明確にしてから適切な分散関数を選択することで、正確な分析結果を得られます。
※上記コンテンツの内容やソースコードはAIで確認・デバッグしておりますが、間違いやエラー、脆弱性などがある場合は、コメントよりご報告いただけますと幸いです。
ITやプログラミングに関するコラム
- Canvaとは?使い方やアカウント登録などを初心者向けに解説
 git configで設定情報を確認・表示する方法
git configで設定情報を確認・表示する方法 「Pythonはやめとけ」と言われる理由と学習するメリット
「Pythonはやめとけ」と言われる理由と学習するメリット Ubuntuのversionを確認する方法
Ubuntuのversionを確認する方法 Geminiで画像を生成する方法|ChatGPTとの比較結果も紹介
Geminiで画像を生成する方法|ChatGPTとの比較結果も紹介