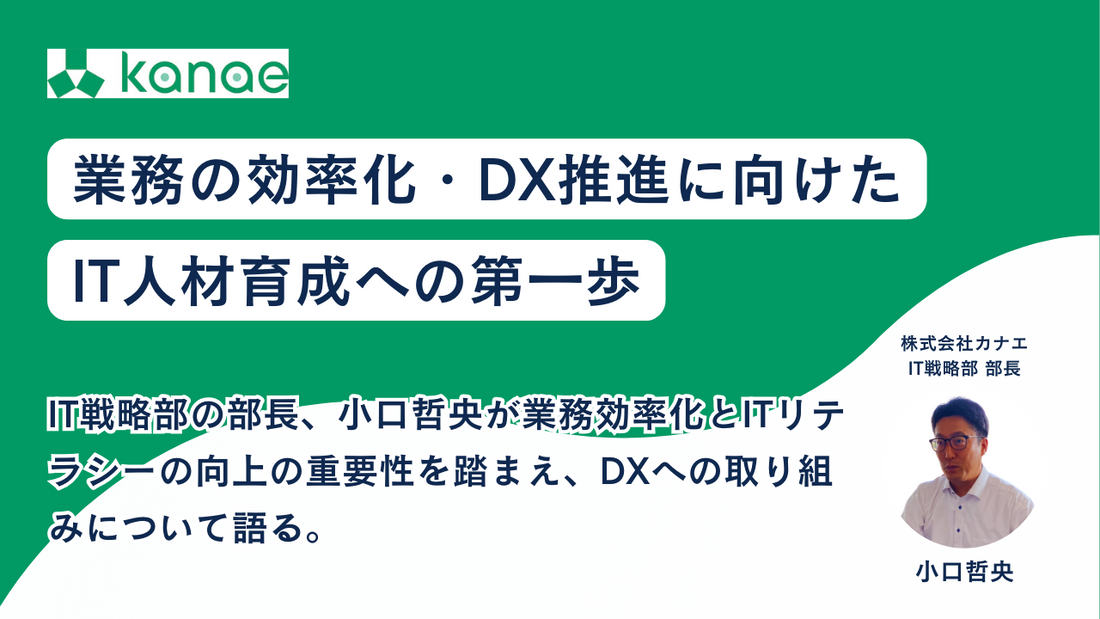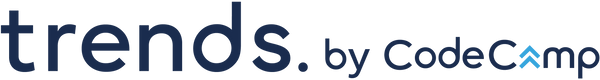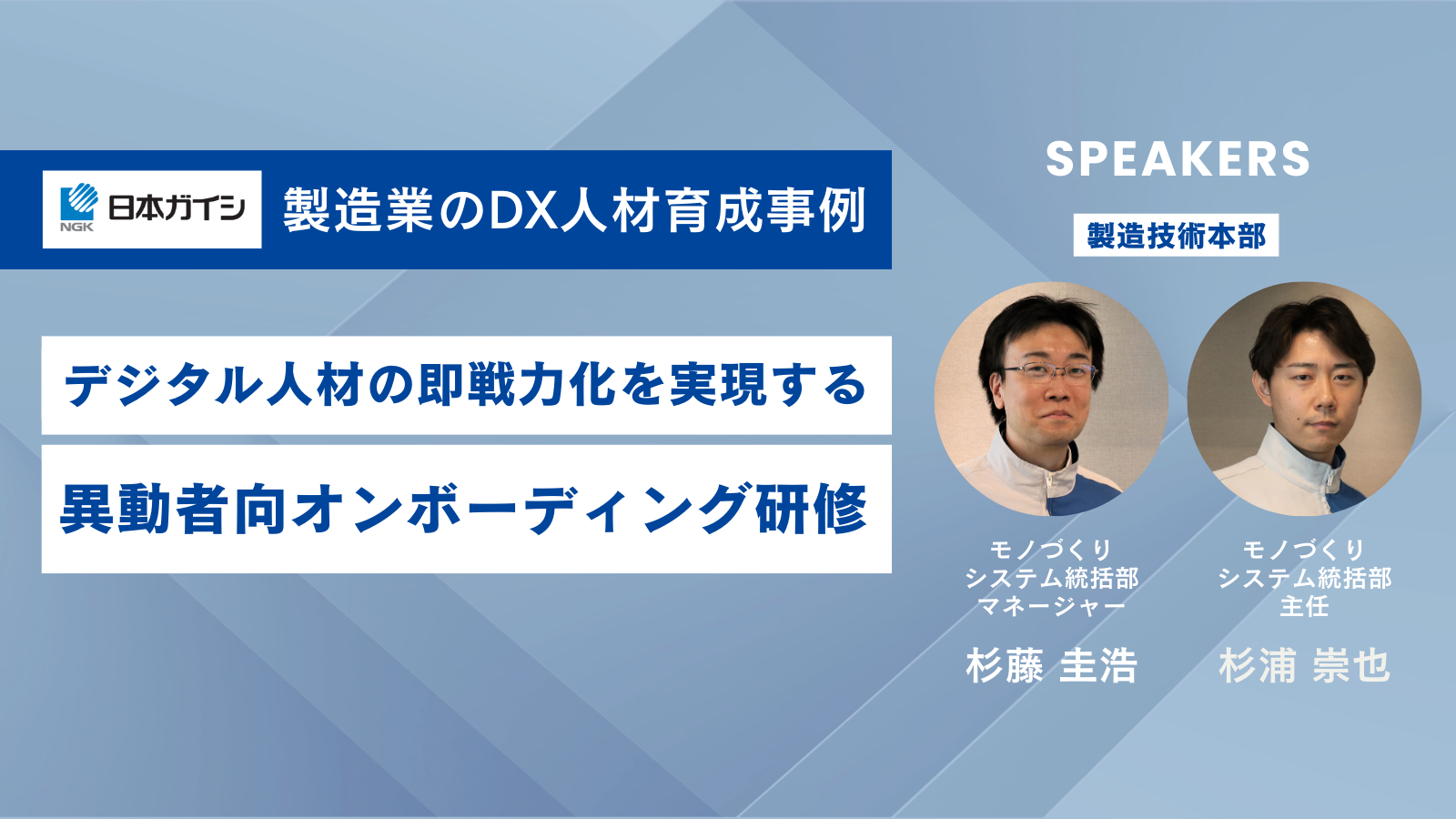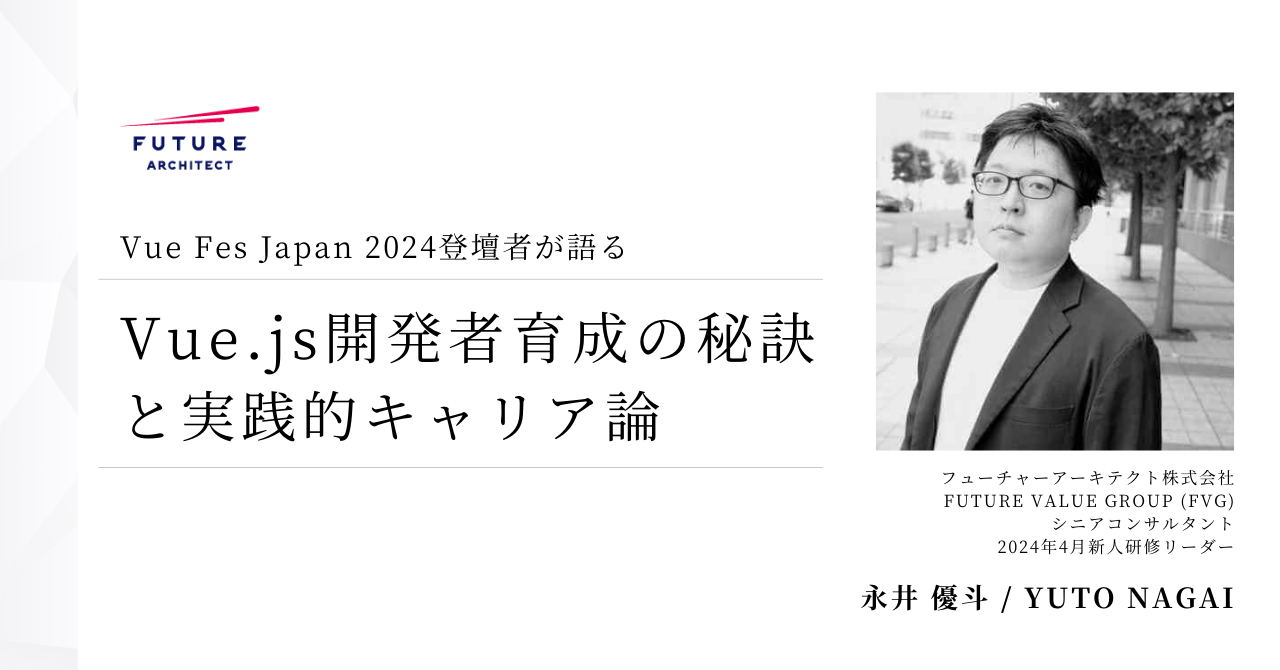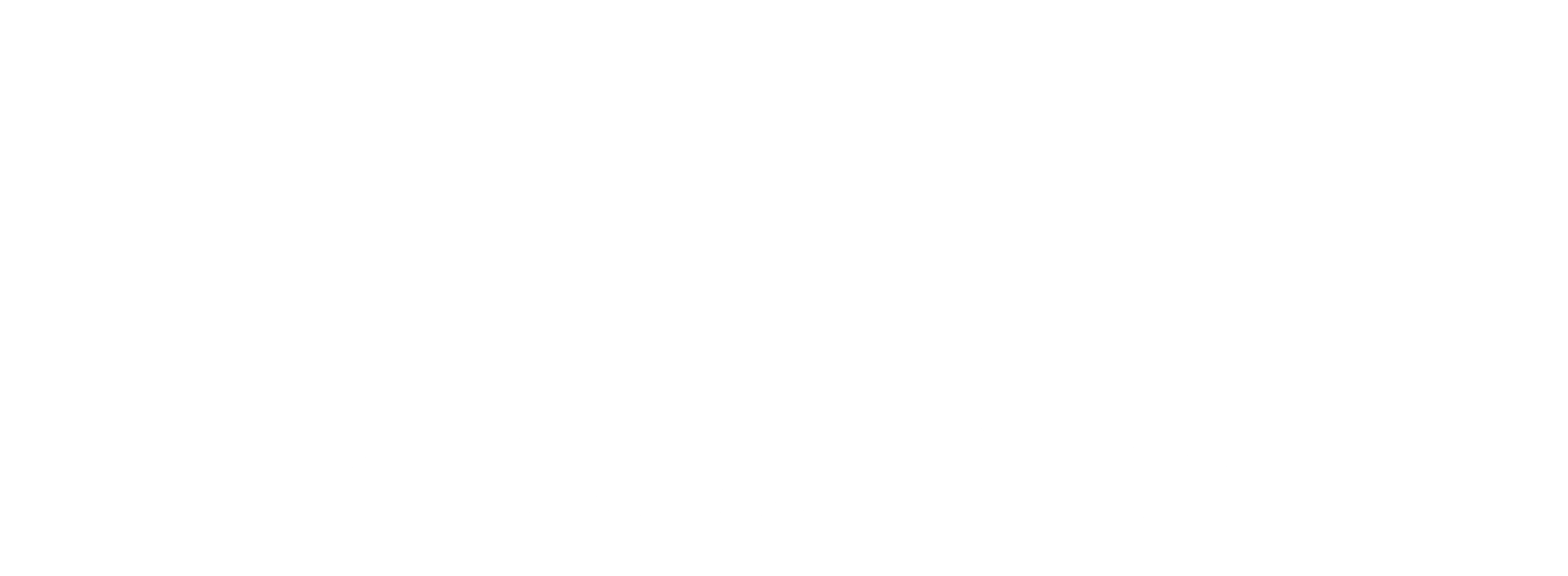【Python】shape属性の使い方を簡単に解説
公開: 更新:Pythonのshape属性は、主にNumPyライブラリの配列(ndarrayオブジェクト)やPandasライブラリのデータフレーム(DataFrameオブジェクト)において利用されます。
shape属性を利用することで、配列やデータフレームの各次元における要素数を取得できます。
特にデータの解析や加工を行う際、データ構造を理解するために非常に有用です。
NumPyライブラリを利用したshape属性の使用例
以下に、NumPyライブラリを利用したshape属性の基本的な使用例を示します。
import numpy as np
# 配列の作成
a = np.array([[5, 6, 7], [8, 9, 10], [11, 12, 13]])
b = np.array([[14, 15], [16, 17]])
# shapeの取得
print(a.shape) # (3, 3)
print(b.shape) # (2, 2)
import numpy as npはNumPyライブラリをインポートしており、以降のコードでNumPyの関数や属性を利用できるようにしています。
a = np.array([[5, 6, 7], [8, 9, 10], [11, 12, 13]])とb = np.array([[14, 15], [16, 17]])は、それぞれ3x3と2x2の2次元配列を作成しています。
print(a.shape)は2次元配列aの形状を出力しており、出力結果は(3, 3)となるので、配列aが3行3列の要素を持っていることを示しています。
print(b.shape)は2次元配列bの形状を出力しており、出力結果は(2, 2)となるので、配列bが2行2列の要素を持っていることを示しています。
shape属性を利用することで、配列の各次元における要素数を瞬時に理解できるので、配列のサイズが大きくても構造を簡単に把握することが可能です。
【PR】プログラミングや生成AIを無料で学べる「コードキャンプフリー」
配列の形状を変更する際はreshape()メソッドを利用する
また、shape属性は読み取り専用であり、直接変更することはできないので、配列の形状を変更する際はreshape()メソッドを利用します。
# 配列の形状変更
reshaped_array = a.reshape(1, 9)
print(reshaped_array.shape) # (1, 9)
reshaped_array = a.reshape(1, 9)は、配列aの形状を1行9列に変更しています。
print(reshaped_array.shape)は変更後の配列の形状を出力しており、出力結果は(1, 9)となります。
上記は、配列が1行9列の要素を持っていることを示しています。
shape属性やreshape()メソッドを利用することで、配列の形状を効率的に操作できるようになります。
今まで解説してきた上記のような機能は、データ分析や機械学習のタスクにおいて、データの前処理を行う際に非常に重要なので、しっかり理解しておくことをおすすめします。
※上記コンテンツの内容やソースコードはAIで確認・デバッグしておりますが、間違いやエラー、脆弱性などがある場合は、コメントよりご報告いただけますと幸いです。
ITやプログラミングに関するコラム
 【Python】仮想環境から抜ける方法
【Python】仮想環境から抜ける方法 【Python】文字列から改行コードを除去する方法
【Python】文字列から改行コードを除去する方法 【Python】10回の繰り返し処理を実装する方法
【Python】10回の繰り返し処理を実装する方法 【Python】df(DataFrame)とは?基本的な使い方やデータ操作について解説
【Python】df(DataFrame)とは?基本的な使い方やデータ操作について解説 【Python】指定のファイルがあれば削除する方法
【Python】指定のファイルがあれば削除する方法
ITやプログラミングに関するニュース
 Azure SQL Managed InstanceがVector型Public Preview対応開始、AI駆動アプリケーション開発の効率化を実現
Azure SQL Managed InstanceがVector型Public Preview対応開始、AI駆動アプリケーション開発の効率化を実現 GoogleがGmailアプリにGeminiサマリーカードを導入、メール要約の自動表示機能が利用可能に
GoogleがGmailアプリにGeminiサマリーカードを導入、メール要約の自動表示機能が利用可能に ZenchordとNottaが共同開発したAIイヤホンZenchord 1をMakuakeで先行公開、音声認識から議事録作成まで自動化
ZenchordとNottaが共同開発したAIイヤホンZenchord 1をMakuakeで先行公開、音声認識から議事録作成まで自動化 Ideinが音声解析AIサービス「Phonoscape」の提供を開始、対面接客現場での会話データ活用が可能に
Ideinが音声解析AIサービス「Phonoscape」の提供を開始、対面接客現場での会話データ活用が可能に Microsoftが.NET 10 Preview 4でdotnet run app.cs機能をリリース、プロジェクトファイル不要でC#実行が可能に
Microsoftが.NET 10 Preview 4でdotnet run app.cs機能をリリース、プロジェクトファイル不要でC#実行が可能に