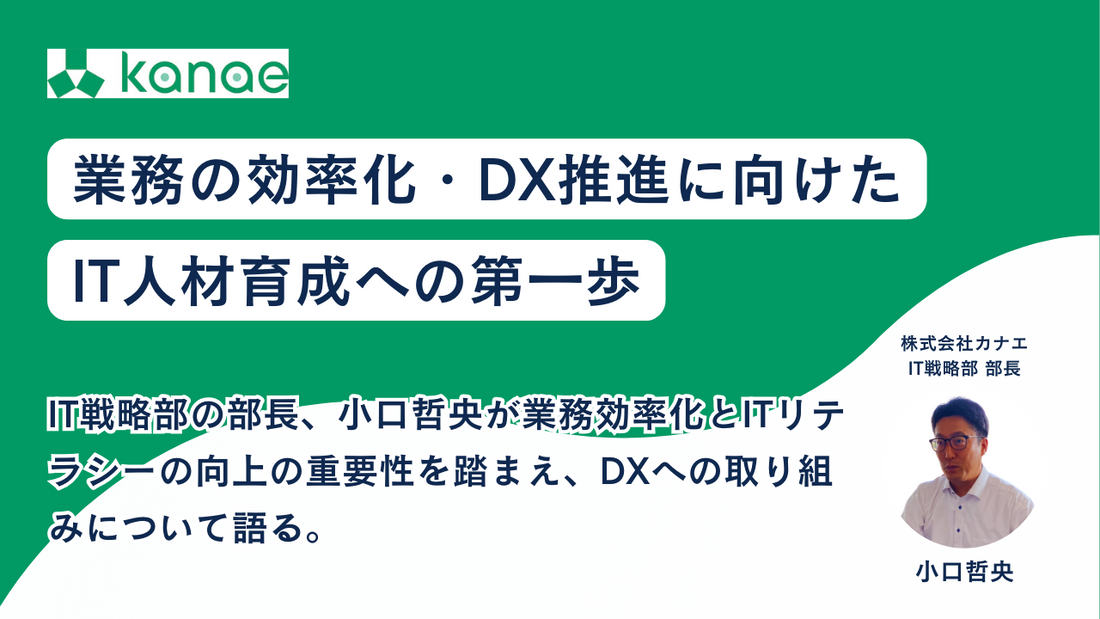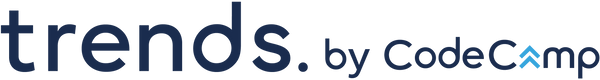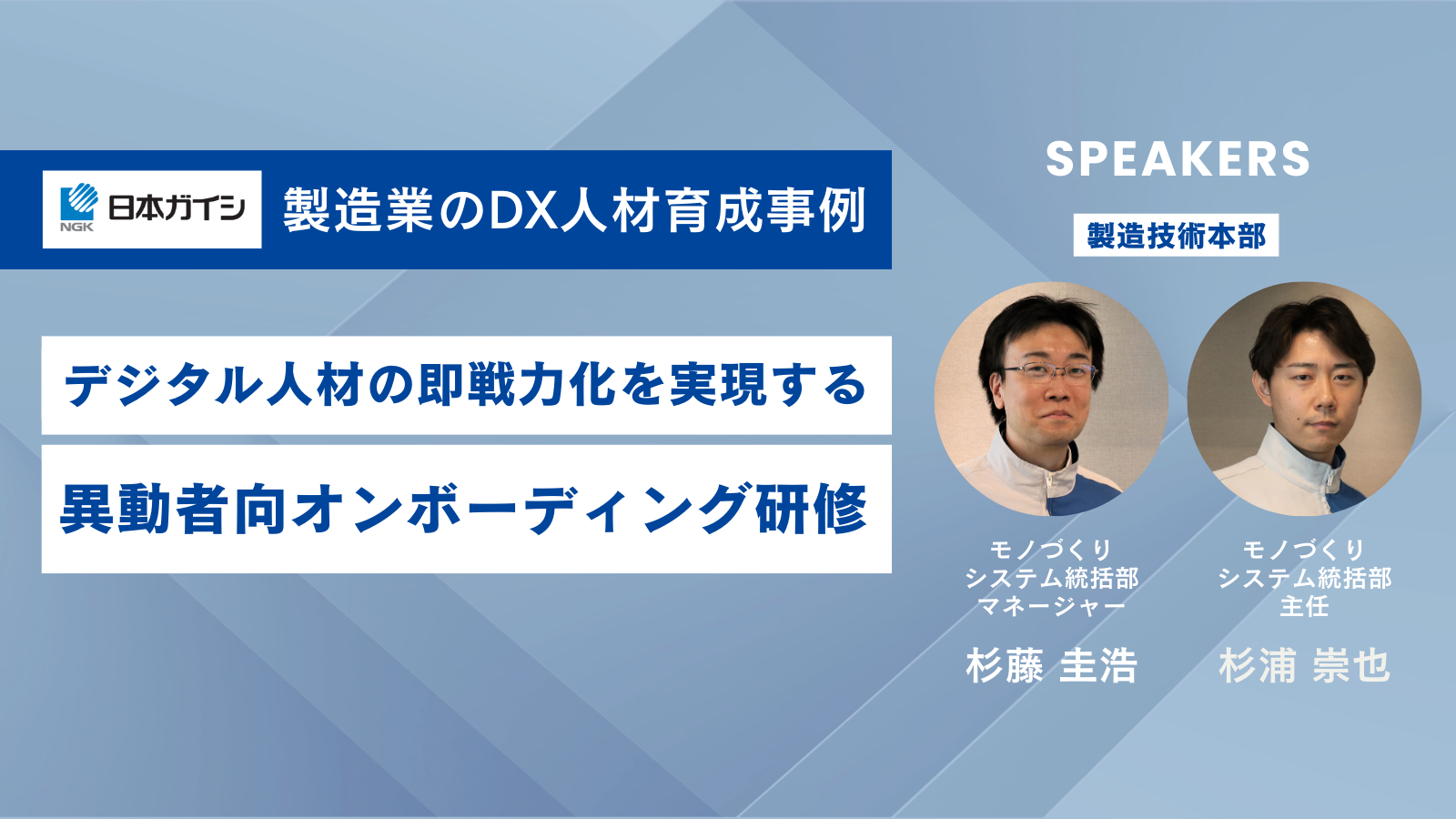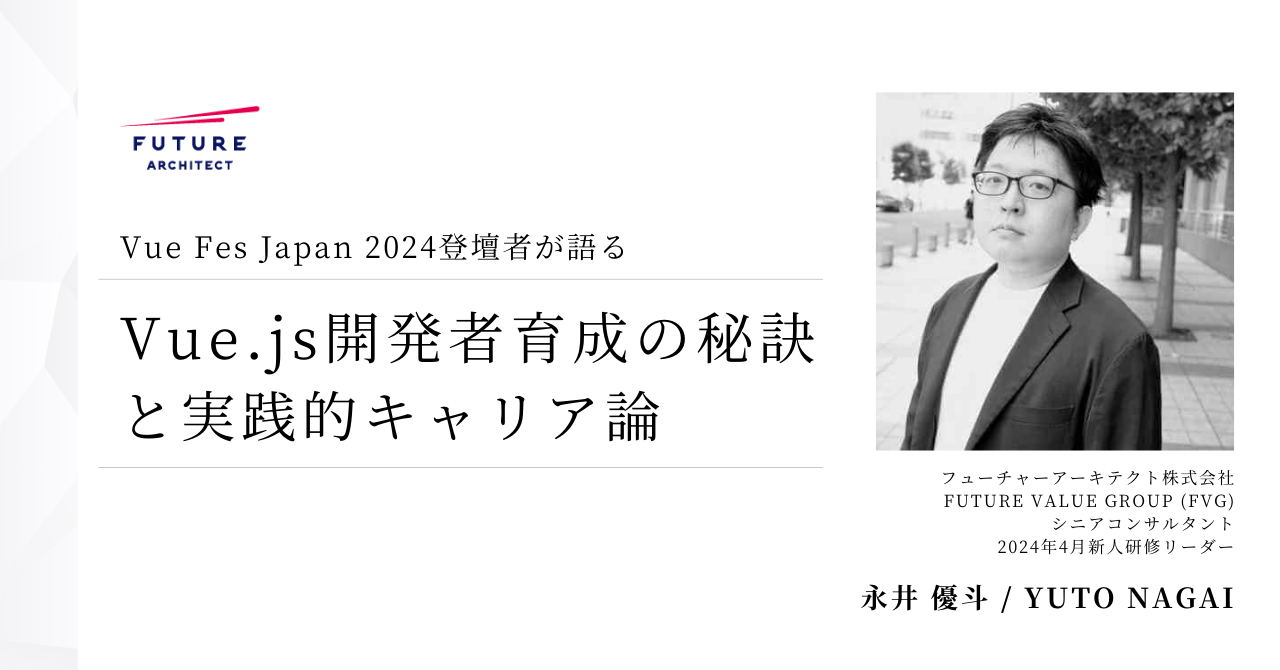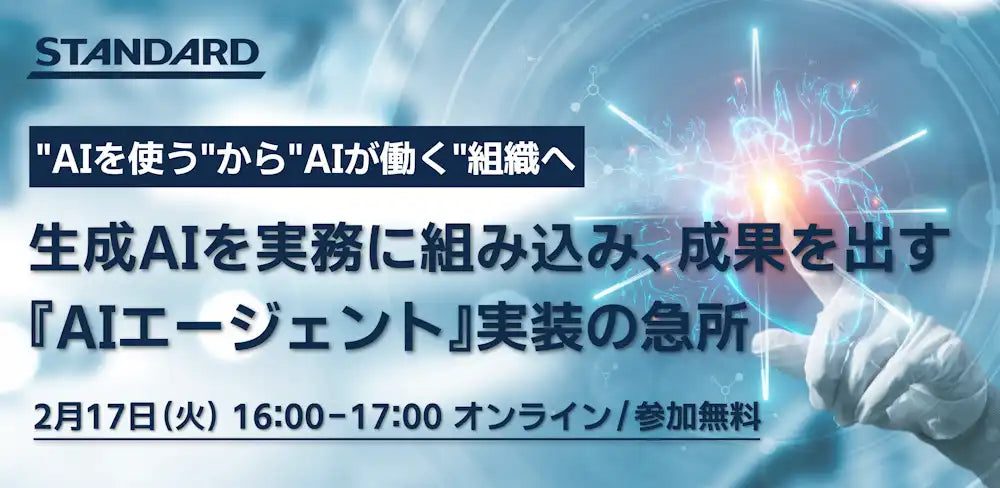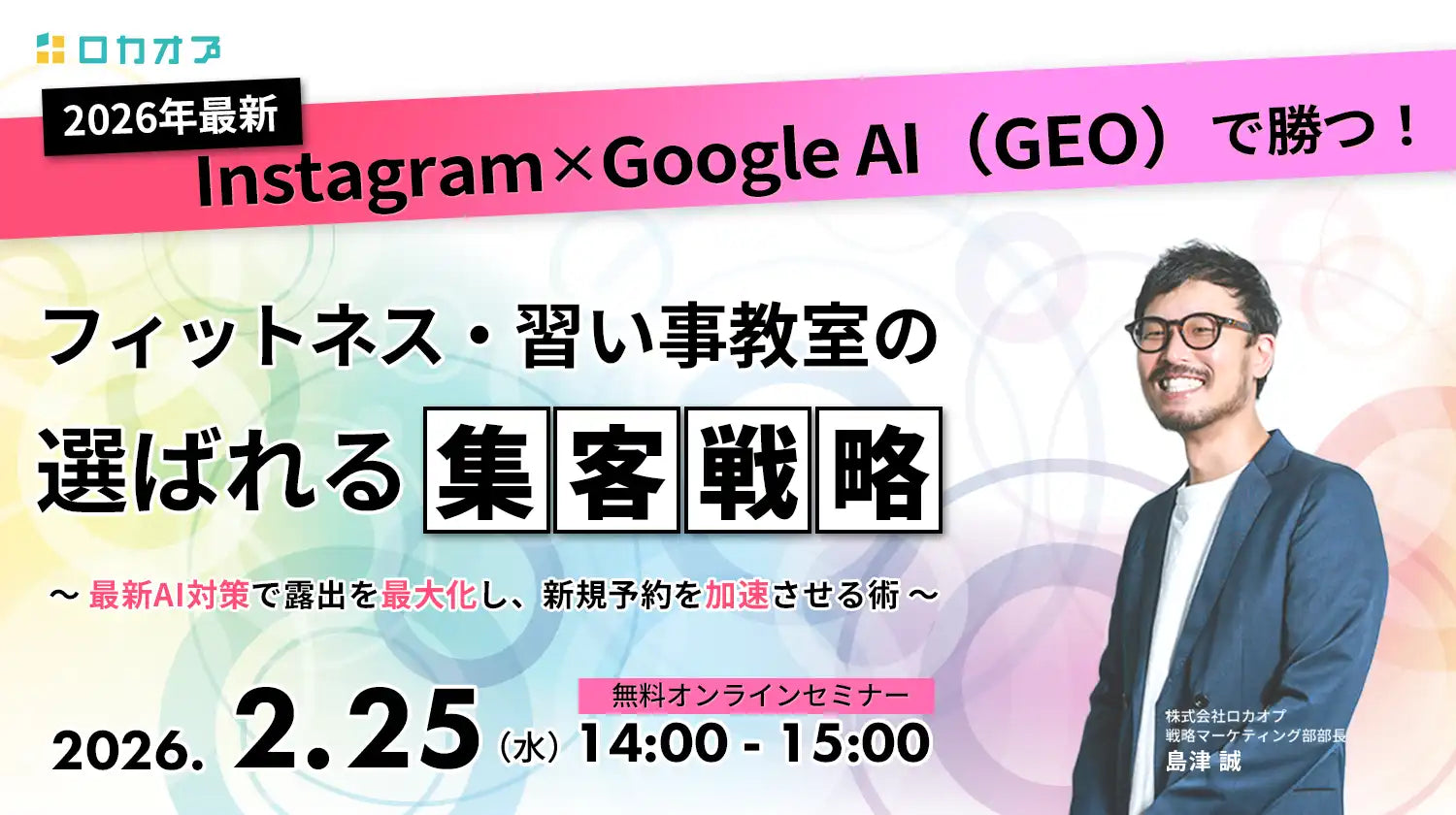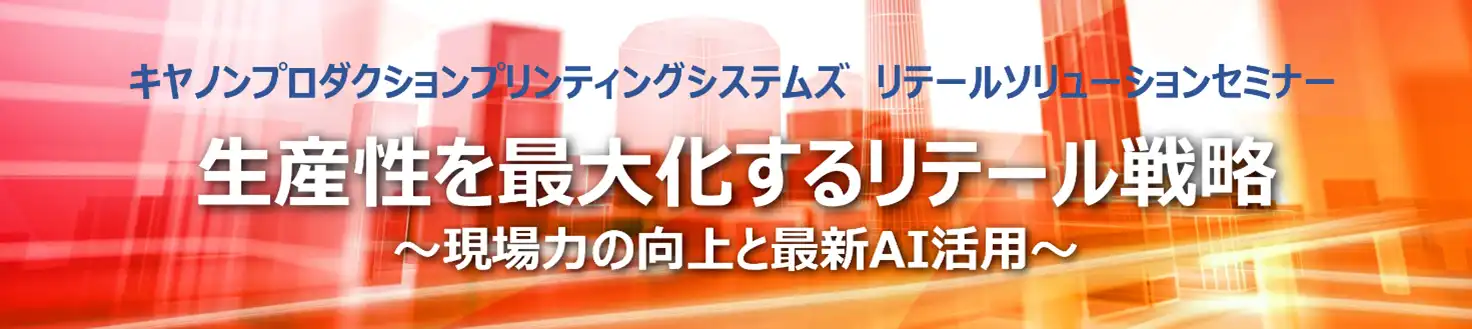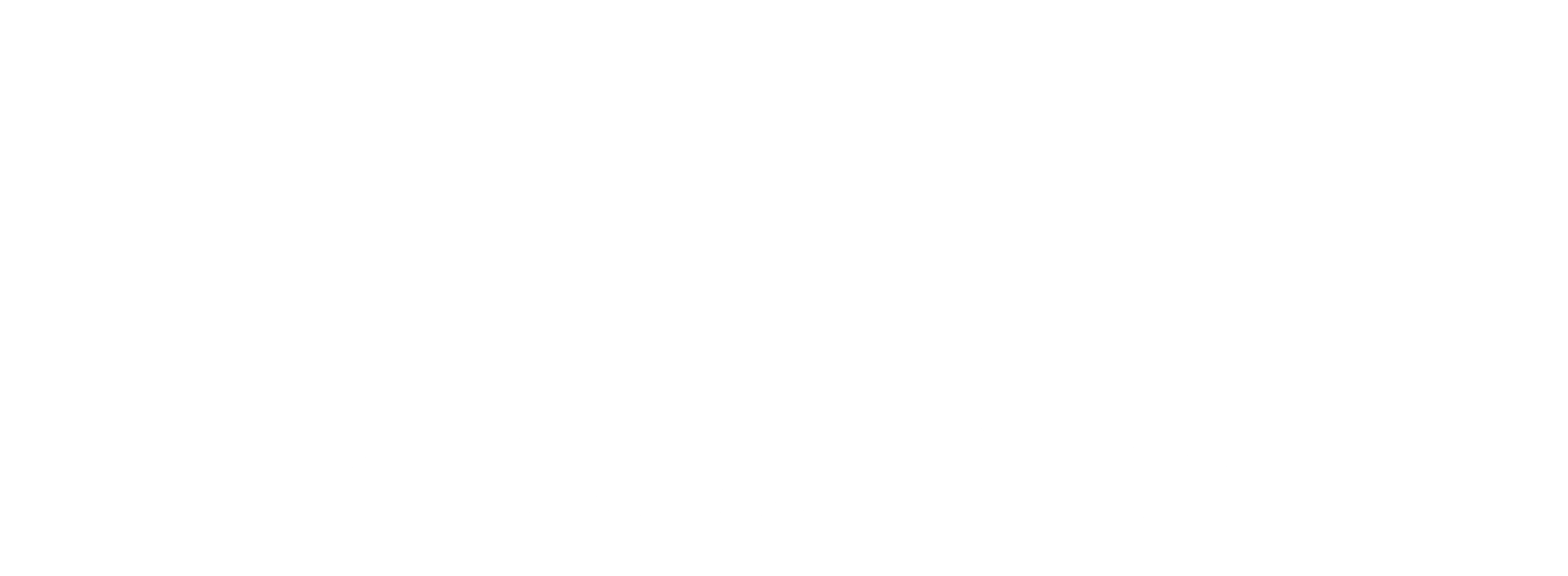スプレッドシートのTTEST関数とは
TTEST関数は2つのデータ群が同じ平均値を持つ母集団から取り出されたものかどうかを判定するための統計関数です。この関数は2つの標本データセットが統計的に有意な差を持つかどうかを確率値として返却します。
TTEST関数の基本構文は「TTEST(配列1, 配列2, 尾部, 検定の種類)」となっており、4つの引数を指定して実行します。この関数は英語名ではT.TESTと表記されることもあり、どちらの表記でも同様の結果が得られるのです。
【PR】プログラミングや生成AIを無料で学べる「コードキャンプフリー」
TTEST関数の引数設定方法
第一引数と第二引数にはそれぞれ比較対象となるデータ範囲を指定し、両方の範囲は同じ数のデータポイントを持つ必要があります。データ範囲は「A1:A10」のような形式で指定し、数値データのみが有効となります。
=TTEST(A1:A5, B1:B5, 2, 1)第三引数の尾部は分布の裾の数を指定し、1を設定すると片側検定、2を設定すると両側検定が実行されます。両側検定では統計的差異をより厳密に評価でき、一般的に推奨される設定となっています。
TTEST関数の検定タイプ指定
第四引数の検定の種類では対応のあるt検定は1、等分散の2標本t検定は2、不等分散の2標本t検定は3を指定します。データの性質に応じて適切な検定タイプを選択することで、より正確な統計結果を得られるのです。
=TTEST(C1:C8, D1:D8, 2, 3)関数の戻り値は0から1の間の確率値となり、この値が0.05未満であれば統計的に有意な差があると判断されます。戻り値が小さいほど2つのデータ群の平均値に差がある可能性が高くなることを示します。
※上記コンテンツの内容やソースコードはAIで確認・デバッグしておりますが、間違いやエラー、脆弱性などがある場合は、コメントよりご報告いただけますと幸いです。
ITやプログラミングに関するコラム
- Canvaとは?使い方やアカウント登録などを初心者向けに解説
 git configで設定情報を確認・表示する方法
git configで設定情報を確認・表示する方法 「Pythonはやめとけ」と言われる理由と学習するメリット
「Pythonはやめとけ」と言われる理由と学習するメリット Ubuntuのversionを確認する方法
Ubuntuのversionを確認する方法 Geminiで画像を生成する方法|ChatGPTとの比較結果も紹介
Geminiで画像を生成する方法|ChatGPTとの比較結果も紹介