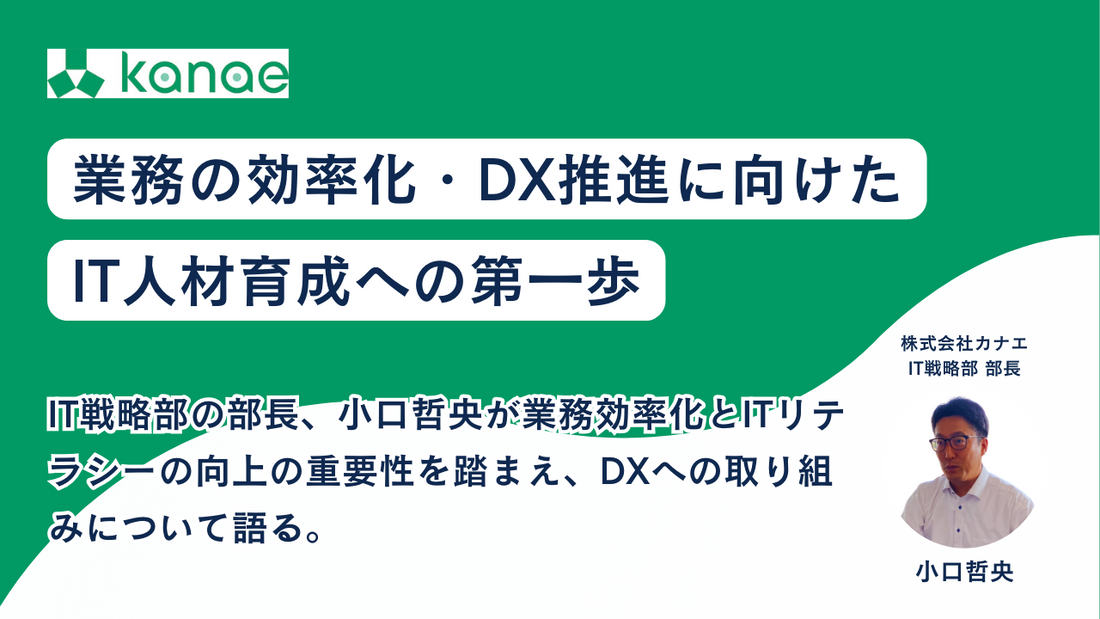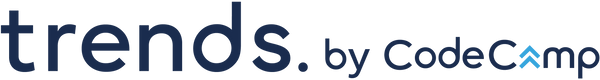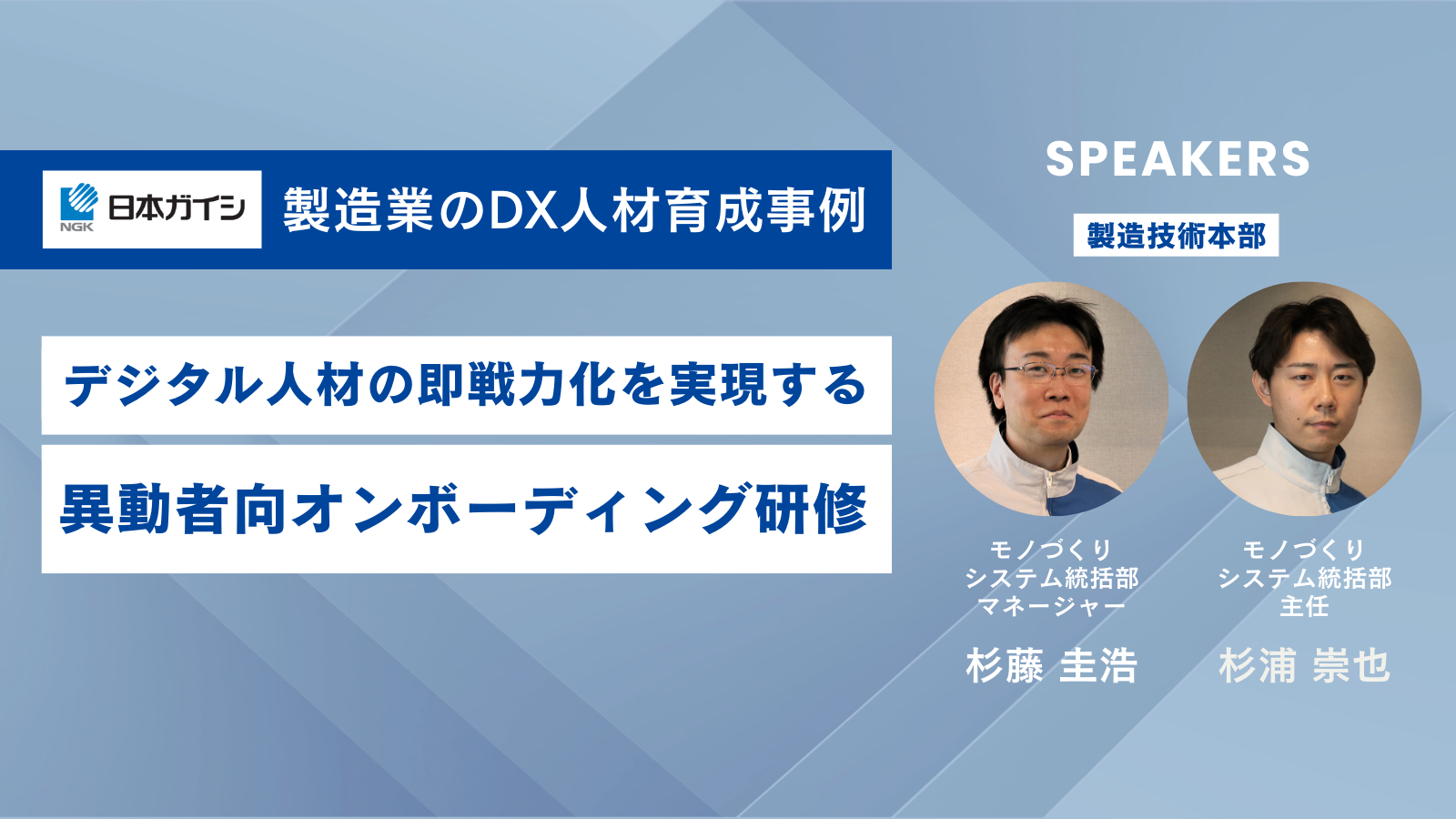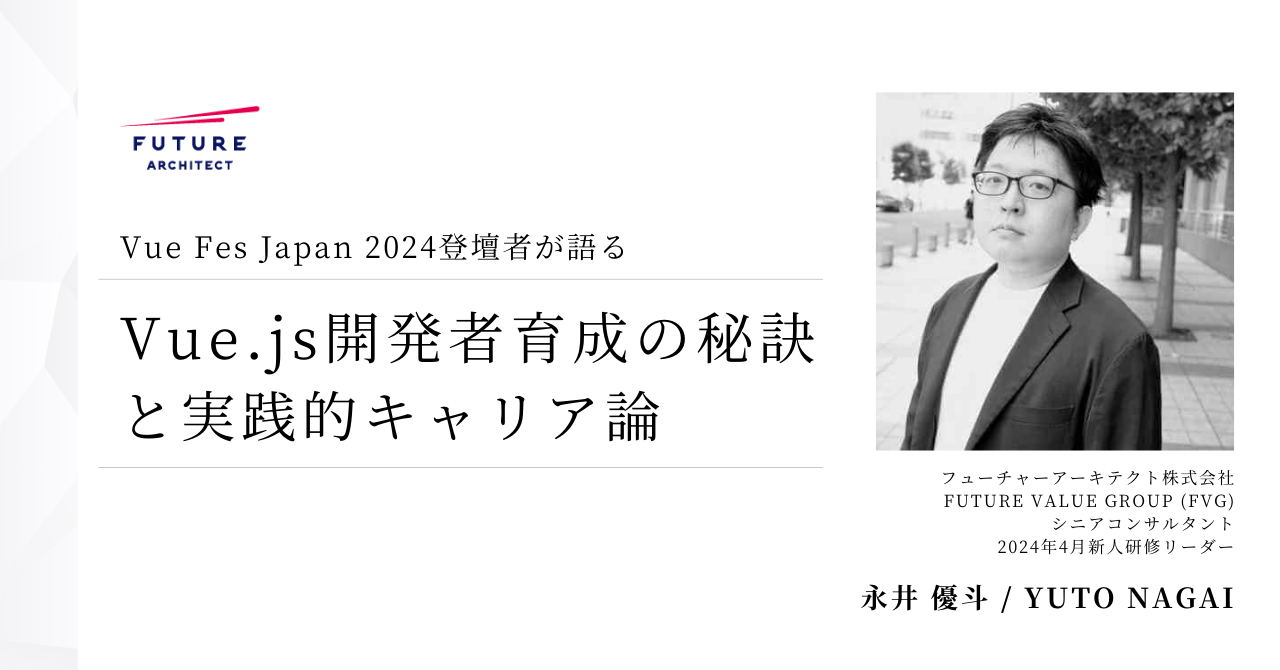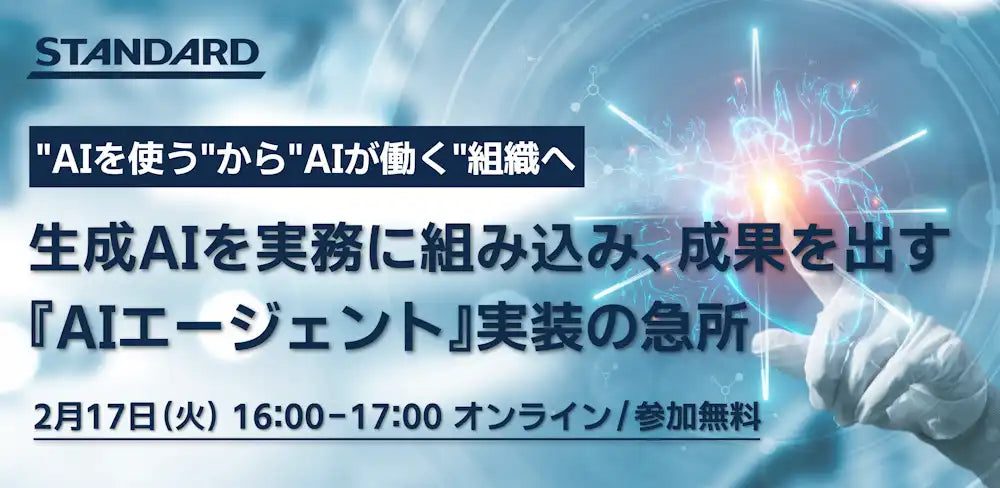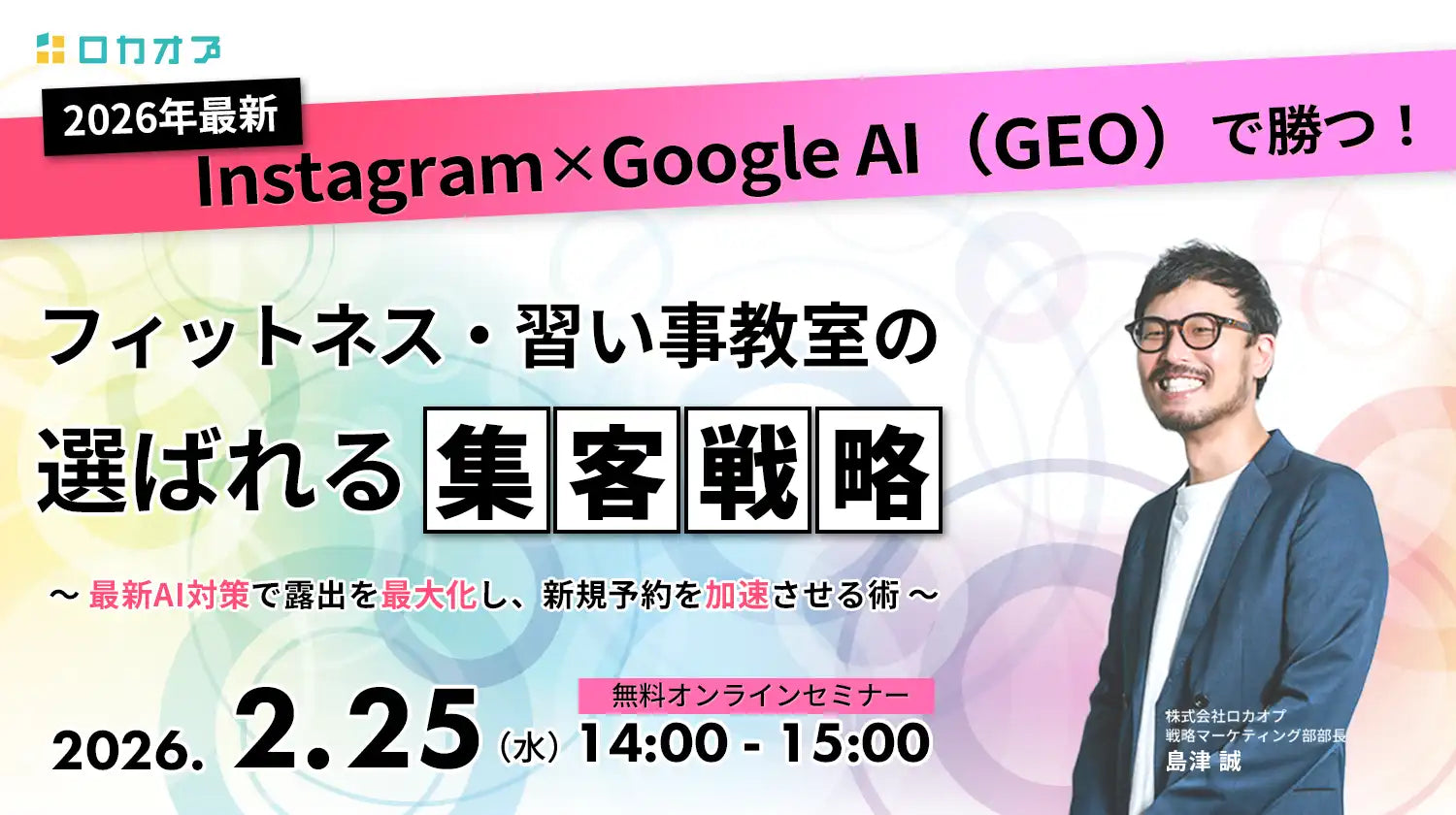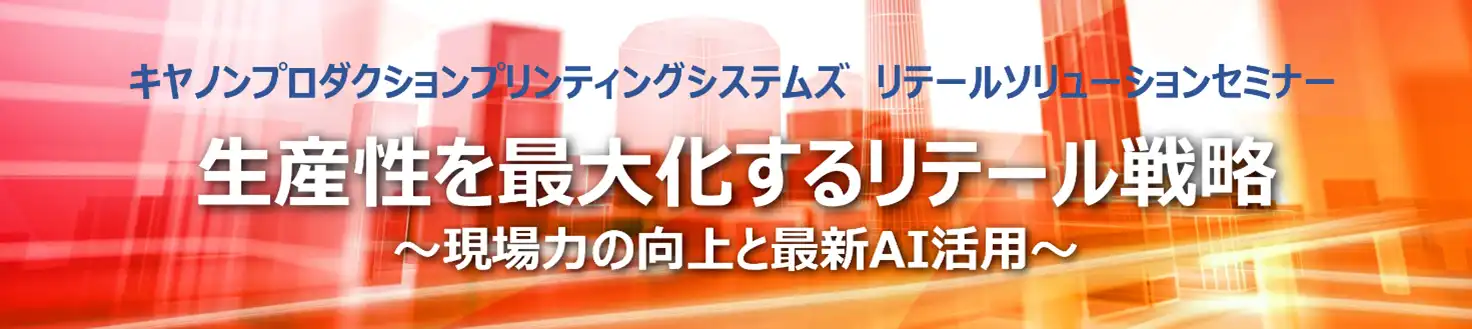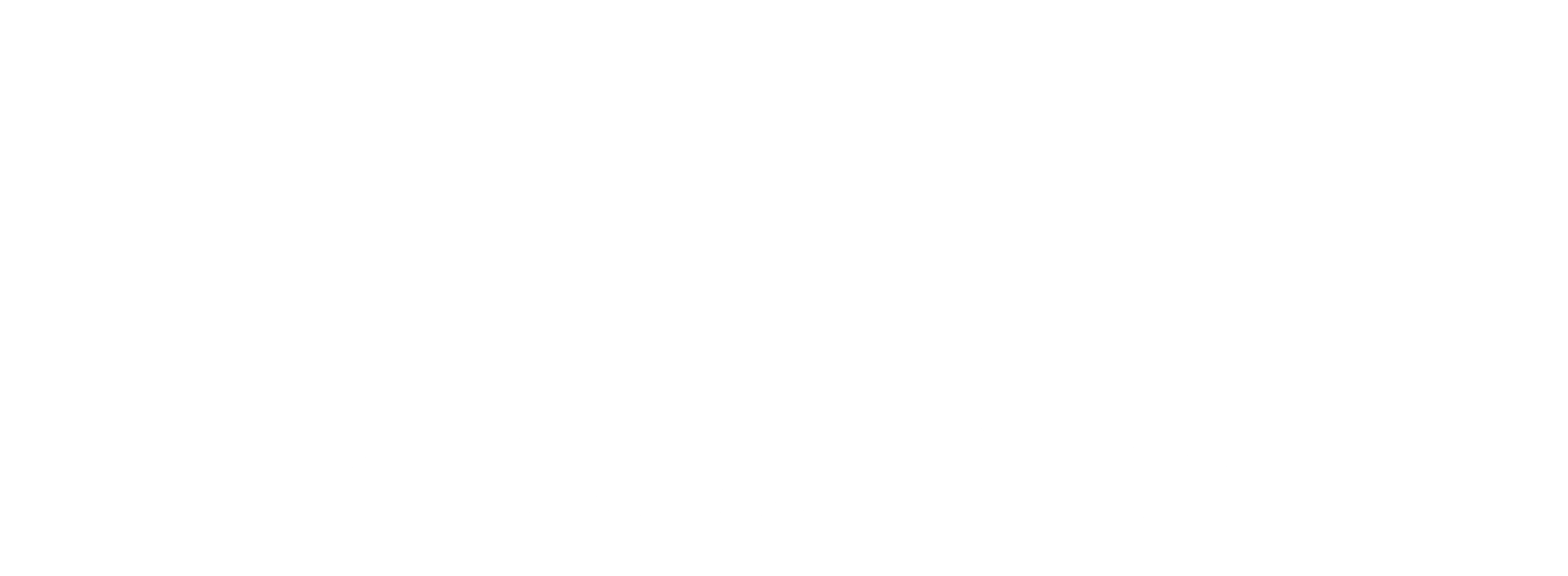スプレッドシートのF.DIST関数とは
F.DIST関数は2つのデータセットに対するF分布の左側確率を計算する統計関数で、フィッシャー・スネデカー分布やスネデカーのF分布とも呼ばれます。この関数は入力値xに基づいて、自由度1と自由度2で定義された分布において特定の値以下の確率を求める際に使用されます。
英名ではF-distribution Functionと呼ばれており、統計学の仮説検定や分散分析において重要な役割を果たしています。関数の結果は累積分布関数または確率密度関数として出力でき、論理値によって形式を切り替えることができます。
【PR】プログラミングや生成AIを無料で学べる「コードキャンプフリー」
累積分布関数での計算方法
cumulative引数にTRUEを指定すると、F.DIST関数は累積分布関数として動作し、指定したx値以下の確率を返します。この形式は統計的検定において、観測値がある閾値以下である確率を求める際に使用されます。
=F.DIST(15.35, 7, 6, TRUE)上記のサンプルコードでは、x値が15.35、第1自由度が7、第2自由度が6の条件で累積分布関数値を計算しています。結果として得られる値は0から1の間の確率値となり、統計的な意思決定に活用できます。
累積分布関数モードでは仮説検定のp値計算に直接使用でき、観測された統計量が偶然によるものかどうかを判断する基準となります。分散分析や回帰分析における分散比の検定において、この計算方法は特に重要な意味を持ちます。
確率密度関数での活用事例
cumulative引数にFALSEを指定した場合、F.DIST関数は確率密度関数として機能し、特定のx値における分布の密度を返します。この形式は分布の形状を理解したり、特定の値での確率密度を求める際に活用されます。
=F.DIST(A2, B2, C2, FALSE)セル参照を使用したサンプルでは、A2セルのx値、B2セルの第1自由度、C2セルの第2自由度を使って確率密度を計算しています。この方法により、データの変更に応じて自動的に計算結果が更新される動的な分析が可能になります。
確率密度関数モードは分布の最頻値や分布形状の可視化に適しており、グラフ作成時の各点の密度値計算に使用されます。統計的モデリングにおいて、観測データの分布特性を詳細に分析する際にこの機能は欠かせません。
※上記コンテンツの内容やソースコードはAIで確認・デバッグしておりますが、間違いやエラー、脆弱性などがある場合は、コメントよりご報告いただけますと幸いです。
ITやプログラミングに関するコラム
- Canvaとは?使い方やアカウント登録などを初心者向けに解説
 git configで設定情報を確認・表示する方法
git configで設定情報を確認・表示する方法 「Pythonはやめとけ」と言われる理由と学習するメリット
「Pythonはやめとけ」と言われる理由と学習するメリット Ubuntuのversionを確認する方法
Ubuntuのversionを確認する方法 Geminiで画像を生成する方法|ChatGPTとの比較結果も紹介
Geminiで画像を生成する方法|ChatGPTとの比較結果も紹介