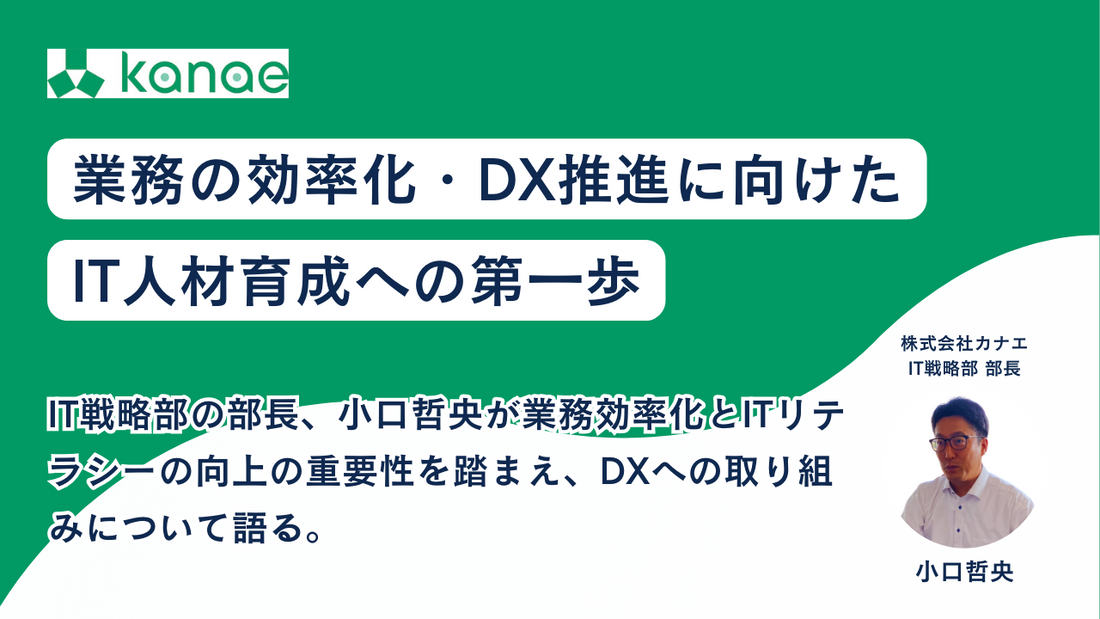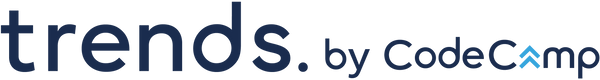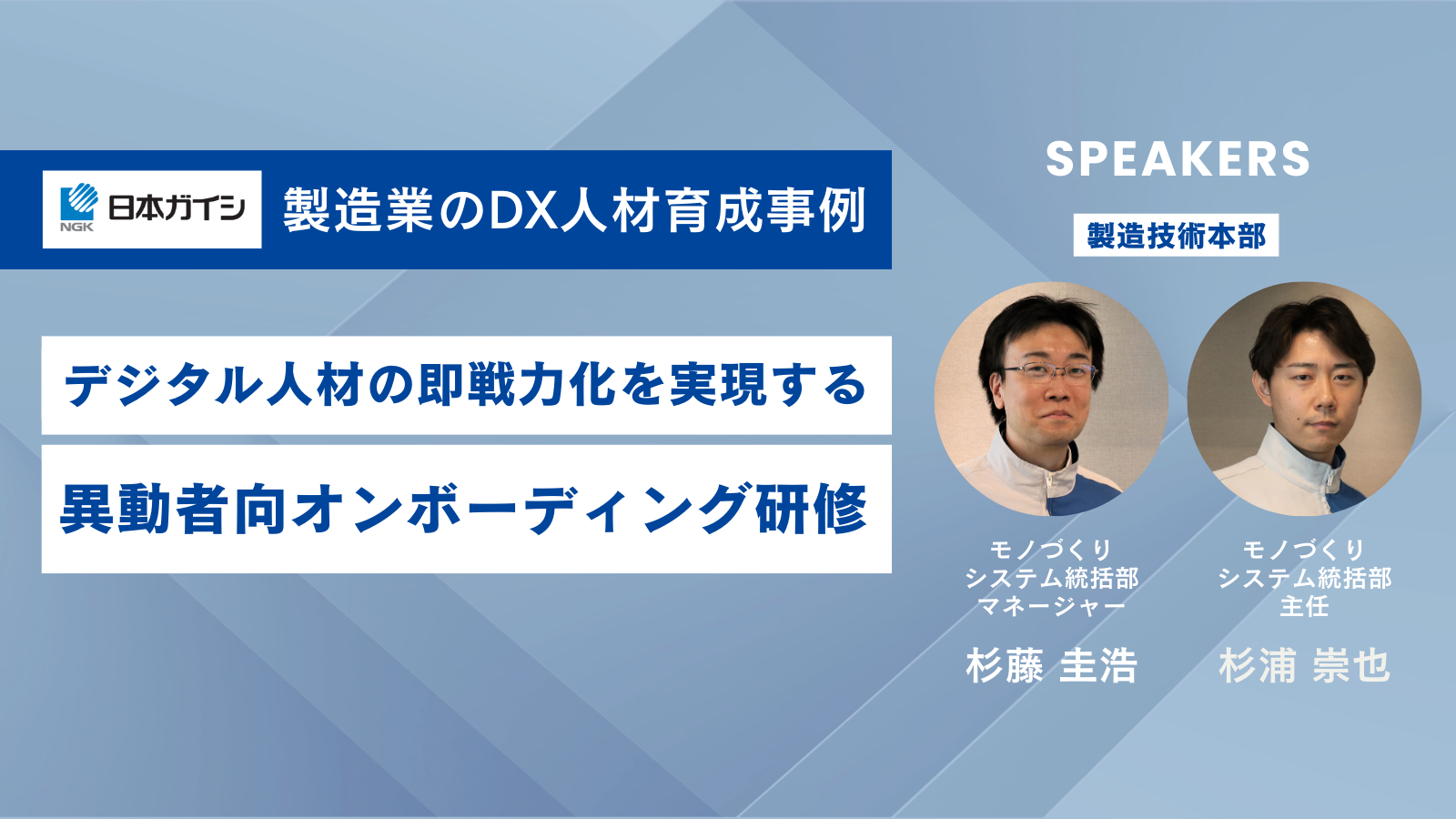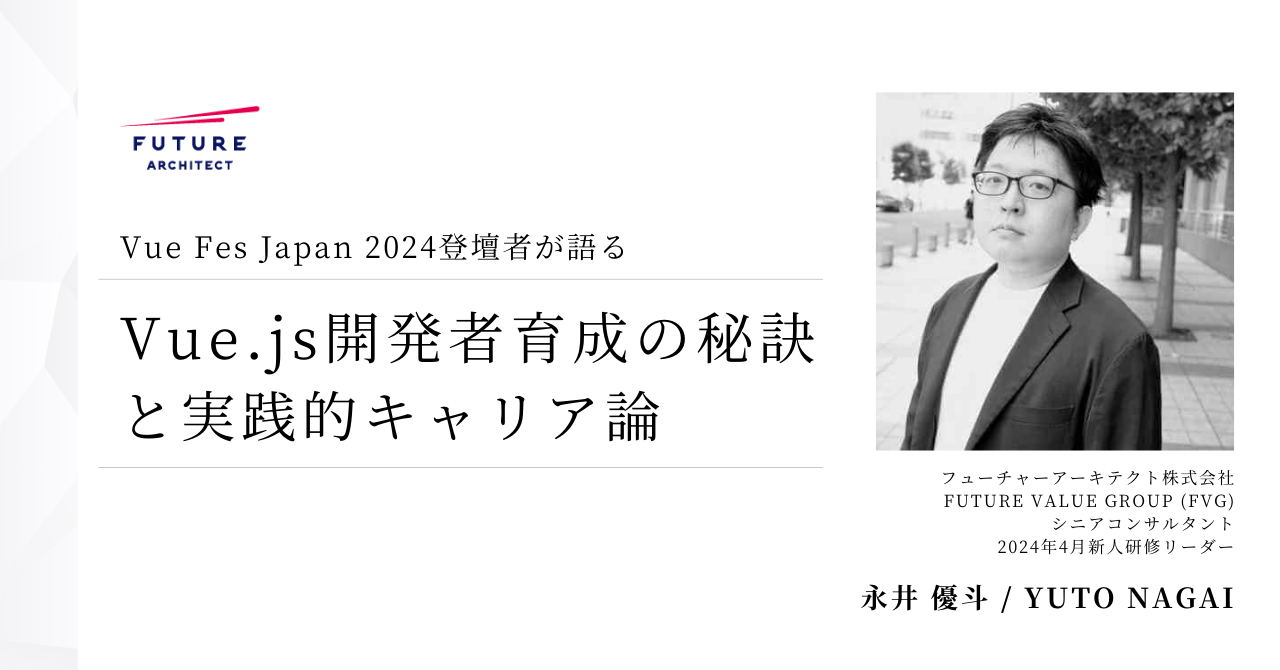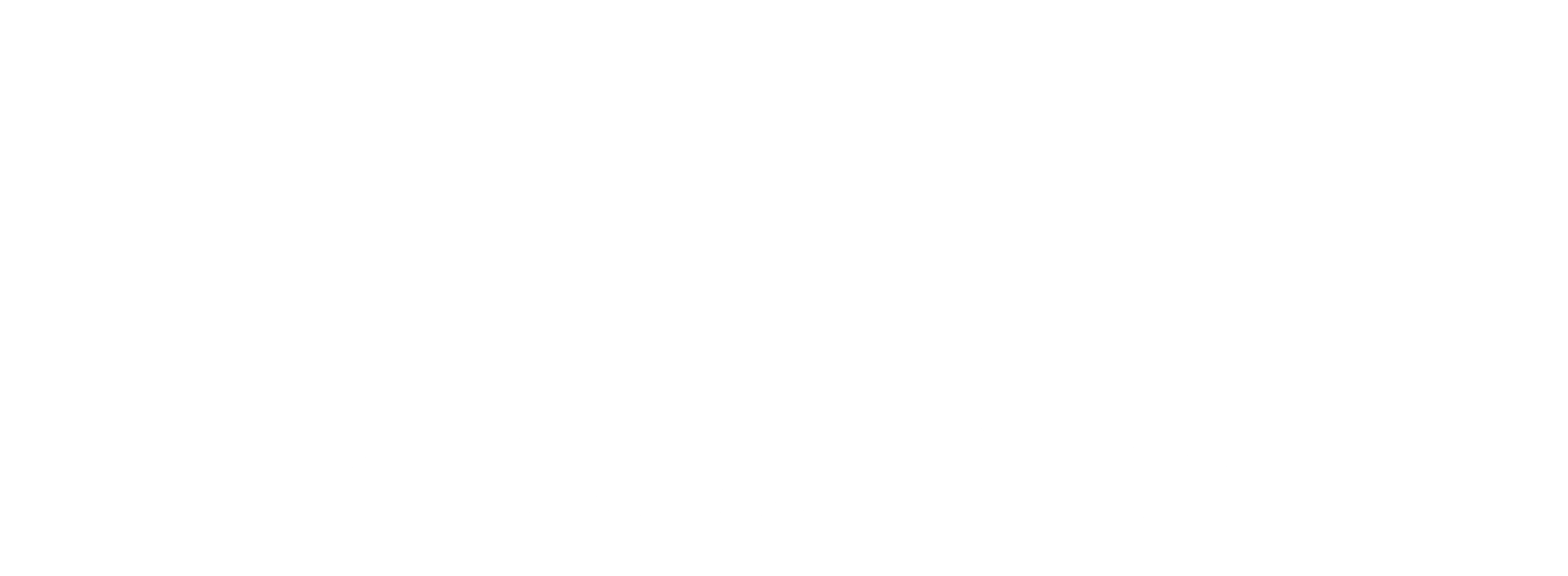前回の記事ではAIの現時点と、AIありきの社会がこれから訪れることについて解説しました。
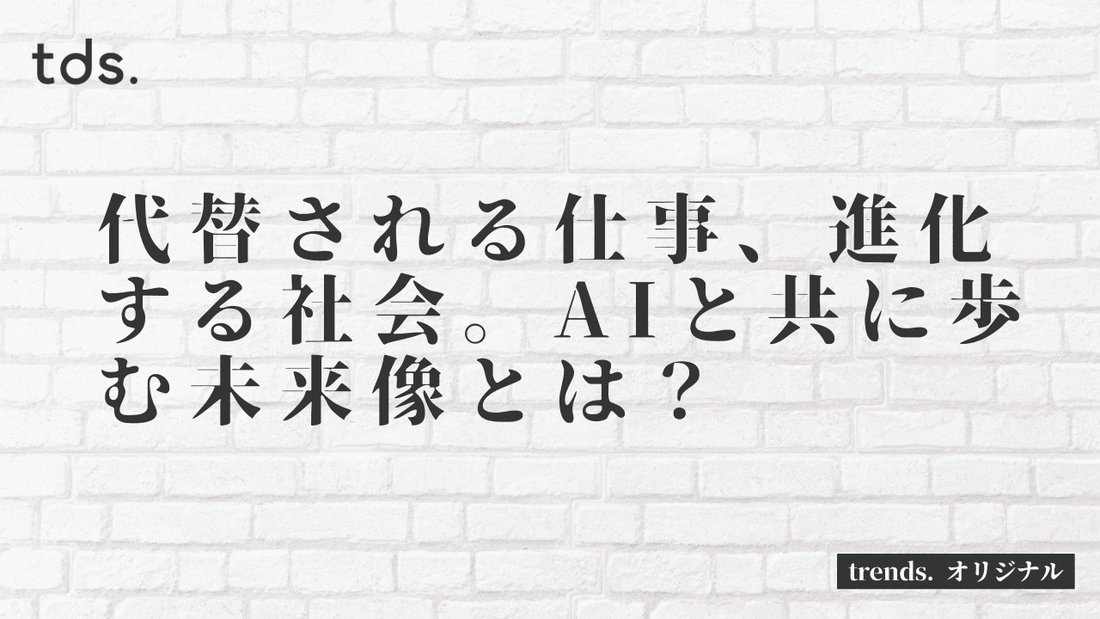
その中でITの基本や仕組みをしっかり理解し、AIを効果的かつ柔軟に使いこなす能力が求められることについても触れています。
本記事ではAIありきの社会で勝ち残るために求められる、アップデートの思考法について解説します。
【IT時代の次に備える】自身をアップデートするための思考法と行動計画

「AIを含めたIT技術の活用が必須になるこれからの時代において、企業および個人のアップデートが必要だ。」
そう言われても具体的に何から始めればいいのか、何をすれば結果に結びつくアップデートが可能なのかわからない方も多いのではないでしょうか。
その普遍的な回答のひとつとして「ITの基礎知識や基本的なスキル、今のAI技術でできることを知ることから始める。」ことが挙げられます。
IT技術の基礎知識やITスキルを習得することで、今自分が属している企業の課題をデジタル化により解決可能かどうか発見する手助けとなるでしょう。
たとえば問い合わせ対応に時間がかかりスタッフの負担が大きいという課題がある場合、AIチャットボットを活用することでその負担を軽減できます。
よくある質問にはAIが即座に回答し、スタッフは複雑な問題や個別対応に集中できる環境を作ることが可能です。
このようにIT技術が得意なことや現状のAI技術でできることを把握することは、業務の一部をデジタル化で効率化するアイデアを出すことにつながります。
IT技術の基礎や実践的なITスキルを身につけるには

IT技術の基礎や実践的なITスキルを身につける方法は、各個人や企業によって異なるのが特徴です。たとえば企業単位で新卒や社員を育成する場合、法人向けのIT研修やeラーニングの利用などが挙げられます。
個人においてはeラーニングやオンライン講座、書籍・動画教材などがよく使用されています。これらの内容あくまでも一例であり、アップデートするための手段は問いません。
とはいえ各手段ごとにメリットとデメリットがあるので、内容がわかりやすいように表でまとめました。
| 手段 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| eラーニング |
|
|
| オンライン講座 |
|
|
| 書籍・動画教材 |
|
|
| 法人向けIT研修 |
|
|
企業であれば予算や人的資本、個人であれば学習時間や目標などで最適な方法が変わります。大切なのは変化する(アップデート)ために行動することです。
すでに成立しているITベースの社会から今後どうなるのかを予測して対応するためにも、自身をアップデートしないとおいて行かれる可能性があります。これはAIに限った話ではなく過去にも起こっている事実です。
過去に起こった新技術による変化
内閣府が公開している「新たな産業変化への対応」[1]ではIoTやAI、ロボット技術などのが混ざり合う技術革新が、第4次産業革命に該当すると記載されています。
一つ目はIoT及びビッグデータである。工場の機械の稼働状況から、交通、気象、個人の健康状況まで様々な情報がデータ化され、それらをネットワークでつなげてまとめ、これを解析・利用することで、新たな付加価値が生まれている。
出典:内閣府「第2章 新たな産業変化への対応(第1節)」
二つ目はAIである。人間がコンピューターに対してあらかじめ分析上注目すべき要素を全て与えなくとも、コンピューター自らが学習し、一定の判断を行うことが可能となっている。加えて、従来のロボット技術も、更に複雑な作業が可能となっているほか、3Dプリンターの発展により、省スペースで複雑な工作物の製造も可能となっている。
このように技術の進化による変化を受け入れることは避けられないでしょう。新技術が社会に及ぼす影響や、それに対する適応の重要性を過去の事例を通して紹介します。
自動車がもたらしたニューヨークの劇的な変化

1900年代初頭のニューヨークは馬車で溢れていました。しかし1908年に手頃な価格で購入できる自動車(T型フォード)が登場し、状況は一変します。
多くの人々が自動車を購入し、道路整備やガソリン供給インフラの発展も進んだことにより、街並みがわずか10年で劇的に変化しました。
この事例では新技術が普及する上でインフラや環境の整備が不可欠であり、環境が整えば社会全体に劇的な変化が起きる可能性を表しています。
自動車に関する近年の例だと自動運転が注目を集めています。たとえばサンフランシスコで一般公開された自動運転サービス「Waymo One」は利用率が約3割で、主に通院などで利用されているようです。
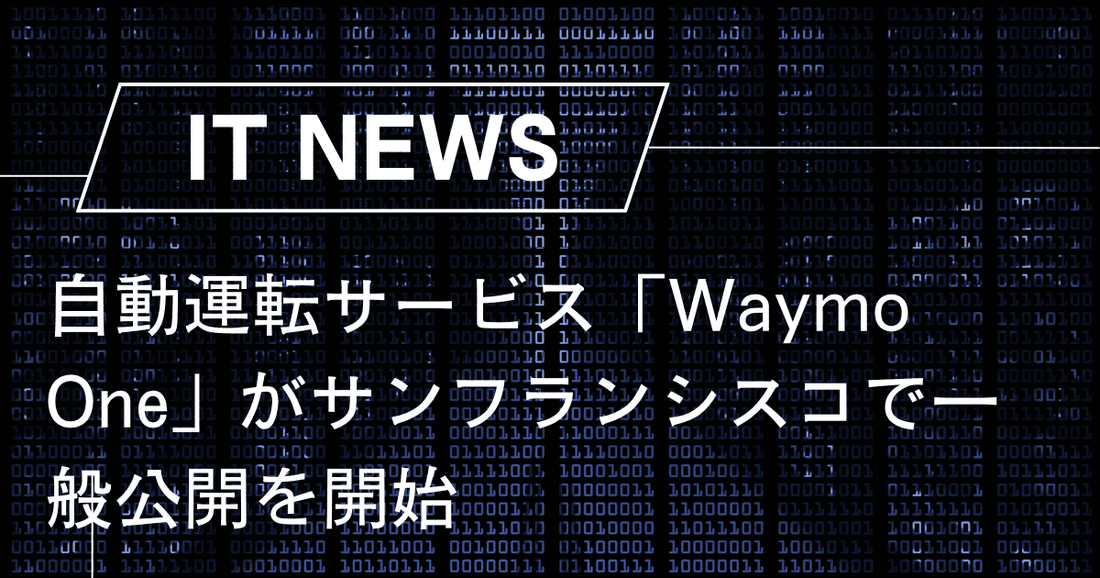
本サービスは2025年に東京での自動運転テストも予定されています。今後はタクシーに代わる存在として街に馴染んでいく可能性もあるでしょう。[2]
鉄道業界が置いていかれた本当の理由

アメリカで車の普及が進む中、遠くへの移動手段においては飛行機が台頭していました。それまでは鉄道が主要な移動手段でしたが、車や飛行機といった新技術が普及する中で衰退していきます。
しかしその原因は新技術の台頭だけではなく「鉄道事業」に固執したことも問題だと考えられています。もし車や飛行機といった新しい移動手段を自分たちとは関係ない別業界と捉えず、顧客の視点に立って柔軟に変化していれば、鉄道業界の未来も変わっていたかもしれません。
たとえばドイツの「エアレールサービス」は、鉄道と航空便を一括で予約できる仕組みを提供しています。[3]このサービスにより都市部から空港まで列車でスムーズに移動でき、タクシーや自家用車を利用する必要がなくなるのが特徴です。
また、鉄道駅で航空便のチェックインや荷物の預け入れが可能なため、移動の負担を軽減できるのも魅力です。
このように顧客が求めていることに沿って事業を変化させる視点を持つことで、新しい技術と共存しながら競争力を維持してさらなる成長を遂げられる可能性があります。
上記の事例からもわかる通り、新技術による社会の変化は過去にも起こっています。こうした「変化の波に対応する」のか「取り残されるのか」が、技術革新の時代における成功と失敗を分ける重要な要素となるでしょう。
進化する技術へ適応するために今すべきこと

過去の事例を振り返ると、新しい技術の発展に適応することが個人や企業の未来を大きく左右することがわかります。現代だとそれがAIを含めたIT技術だと言えるでしょう。
ITベースの社会で新たな機会を得る人々がいる一方で、変化を拒んだり適応が遅れたりすることで市場から取り残されるリスクもあります。
重要なのは技術そのものを恐れるのではなく、それが生み出す変化に対応するために行動し続けること。すなわちアップデートすることです。
ガソリン車の普及が社会に新たな価値を提供したように、AIやIT技術を用いた効率化や新しいビジネスモデルを創出が年々増えています。
だからこそ現在進行中の変化を正しく学び、それに備えることが重要。たとえば前回の記事で紹介したAIの活用事例を通じて、どのように価値を創出し業務を効率化できるのかを理解することもひとつの方法です。
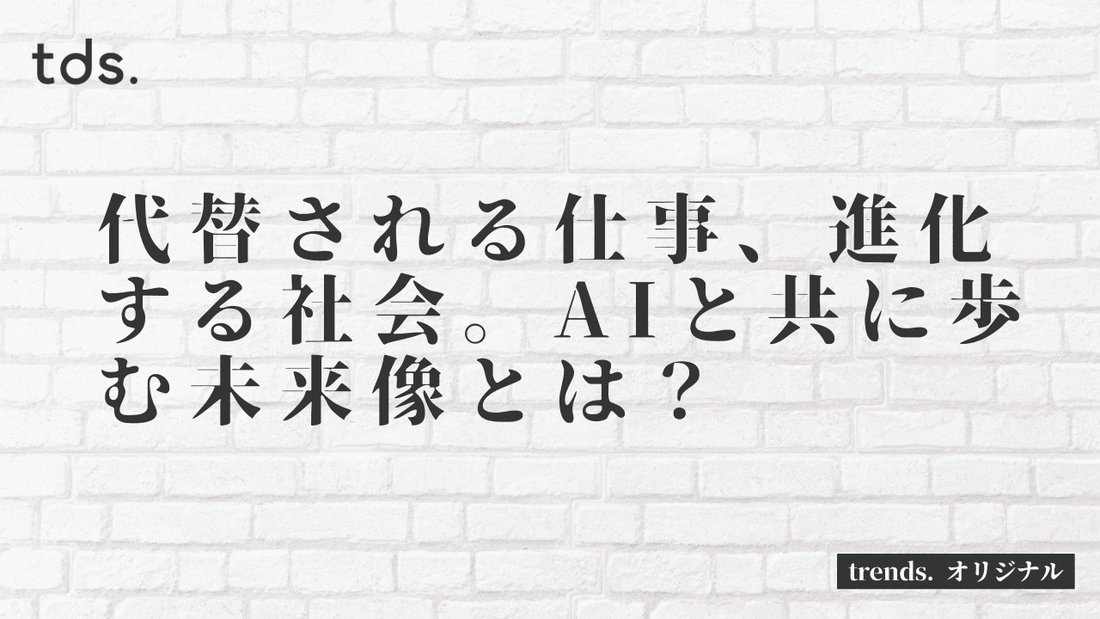
このようにAIについて知ることも立派なアップデートのひとつです。AIのような新技術が出てきたからこそ、うまく使うための土台としてIT技術の基礎を身につけることの重要性は高いと言えます。
【技術の進化を活かすために】売り上げへの貢献と課題解決の視点

技術の進化に適応するためには単にスキルを習得するだけでなく、それをどのように売り上げや課題解決につなげるかを意識することが重要です。特に個人や企業が持続的に成長するためには「売り上げに貢献するスキル」と「課題を発見し解決する能力」を磨くことが必要だと考えられます。
たとえばAIチャットボットを導入して問い合わせ対応を効率化すれば、スタッフの負担を減らしてリソースをより重要な業務に集中させることが可能。これにより顧客満足度の向上や売上増加という、具体的な成果を得られます。
また、変化の激しい環境では現状の課題を正確に見極め、的確な解決策を実行することも重要です。業務の非効率や問題を明らかにし、改善策を実行すれば業務効率や売り上げの向上が期待できます。
最後に取り組みの結果を評価し、改善を繰り返すことで成果を着実に最大化できます。現代ではIT技術の活用が売り上げ向上や、課題解決の大きな手段となり得るでしょう。
時代に合ったアップデートの重要性

結論として現代はITベースの社会であり、個人や企業が失業や倒産、事業停滞を避けるためには自らをアップデートすることが求められます。その方法に正解はありませんが、成果につながらない努力を避けるためにも時代に沿ったアップデートを行うことがポイントです。
現代ではIT技術が基盤となっているため、ITの基礎知識やスキルの習得が適していると考えられます。IT知識やスキルを身につけることで、自分自身や企業の現状を新たな視点で見渡せるようになります。
新しく得た知識を活かせばこれまで見えていなかった課題や解決策を発見し、より良い状態へ導くアイデアが浮かぶはず。これはまさにアップデートされた自分の新しい能力であり、今までできなかった変化を可能にする力と言えるでしょう。
IT技術を武器に加えることで企業の業績向上や課題解決に貢献できる人材や企業へと成長し、今後も長く活躍し続ける未来を築くことが期待できます。
References
- ^ 内閣府. 「第2章 新たな産業変化への対応(第1節)」. https://www5.cao.go.jp/keizai3/2016/0117nk/n16_2_1.html, (参照 2024-12-15).
- ^ GO株式会社. 「GO、Waymo、日本交通 2025年より東京における自動運転技術のテストに向けて協業」. https://goinc.jp/news/pr/2024/12/17/7zxcnor24lj3ts5l3ah2sn/, (参照 2024-12-19).
- ^ JAL. 「エアレールサービス」. https://www.jal.co.jp/del/ja/inter/airport/service/db/, (参照 2024-12-19).